こんにちは。
ここのところコーヒーにハマっております、オイジーです。
というのも、とある取引先様から差し入れでコーヒー豆を頂いたんですね。
しかし、そのコーヒー豆というのが
「挽いてない豆」
だったんです。
グラインダーを持っているかわからない相手に豆の状態のものをプレゼントするのもどうかと思いますが、おかげですっかりハマってしまいまして今では感謝しています。
(ちなみにその前は、蟹の味噌汁の素だったかな。あ、私は甲殻類アレルギーなんですけど)
で、案の定グラインダーを持っていなかったので、Amazonで購入し、自分で挽くことにチャレンジし始めました。
挽いた豆のコーヒーは普通に
「雑味がなくておいしいな~」
くらいに思っていたんですね。
それまではスーパーでドリップパックになっているコーヒー豆を20%オフの日に買い溜めるような生活をしていましたから、全然こだわりもありませんでした。
ただ、毎日数杯は飲むくらいには好きでした。
2、3週間ほどで頂いた豆がなくなったので、元のドリップパックに戻したんです。
そしたら
「・・・まずい」
んです。
「え!?」
と思いました。
明らかに挽きたての豆にはないオフフレーバーを感じるんです。
強めに火を入れ、あえて焦がしたかのようなフレーバー。
その焦げ臭さによって無理に抽出された、味わい。
よくよく味わうと「味が無い」。
極めつけは、家庭用のグラインダーではとても挽けないような細かさで、極限まで豆が持っている味(豆についた焦げ臭さ)を出し切ろうとする企業の戦略まで感じてしまいます。
(ちなみに日本の企業のこういった細かい努力には本当にリスペクトしています。)
そしてこの無理に細かくしたことによる雑味。
細かくしたことによって、酸素と触れる面積の増えた分の酸化のニュアンス。
もしかしたら、その酸化を抑えるための酸化防止剤もあるのかもしれません。
今までなにも感じず、なにも考えずに、普通に美味しいと思って飲んでいたコーヒーが、途端にまずくなったんです。
しかも強烈に・・・
ドリップパックの方がだいぶ安いですから、これは知らなかった方が良かったのかもしれない・・・
そう思いましたが、職業柄非常に良い経験ができたと思うことにしました。
ただで転ぶわけにはいかない。
じゃあこの「なぜ?」を徹底的に追求しようと思ったわけです。
感じなかった味を感じるようになった
恐らくこれが一番の理由でしょう。
「今まで感じなかった味を、感じるようになった」
言い換えると、
「コーヒー豆本来の味を知ってしまった」
ということだと思います。
これの恐ろしいところは、
アップグレードの方はなんなく受け入れられるんですよ。
つまりドリップパックから、自分で挽いたコーヒー豆へと切り替えることは簡単なんです。
しかしダウングレードが全く受け付けない。
そう、身体が、舌が受け入れてくれなくなってしまったんです。
まだ挽いていない豆の袋を開けたときの、香ばしい香り。
ここに余計な焦げは無いんです。
別にお高いコーヒー豆屋さんの豆を使っている訳ではなく、
カルディのマイルドブレンドだって凄く良い香りがするんです。
挽きたての豆のクリアで雑味のなさ。
ちゃんと豆から滲み出る味わいの中域。
アフターに伸びる豆のあまみ。
それも少し冷めてくると凄く際立ちますが、ドリップパックは冷めてくるとどんどん雑味が明瞭になってくるのが分かります。
知らなければよかった・・・
いや、知れてよかった・・・
この思いが交互に着た挙句、それから半年、身体は正直なもので、ドリップパックのコーヒーを受け付けなくなってしまいました。
これでよかったのだろうか・・・
別物であると考えた方がいい。
ドリップパックのコーヒー。それは
・あえて焦がしたかのようなフレーバー
・無理に抽出された雑味のある味わい
・酸化のニュアンス
・中域のスカスカな味わい。
・味わいの大部分は焦げ臭さ
自分で挽いた豆、それは
・焦げではない香ばしさ
・クリアで雑味のない味わい
・中域のある味わい
・アフターに伸びる豆のあまさ
羅列してみると本当に真逆であることが分かります。
これはもはや誰がどう見ても・・・
「別物である」
ということです。
同じ「コーヒー」という名前がついているから、ややこしくなるんです。
「ドリップパックのコーヒー」と「自分で挽いたコーヒー」という別物なんです。
「そば」と「うどん」くらい違うんです。
いや、「パスタ」と「ラーメン」くらい違う。
ジャンルが違う。
だって、
「ある」ものが無くて
「無い」ものがあるんですから。
ワインにも言えること
前置きが長くなってしまいました。
しかし、これと似たようなことはワインにも言えると思うんです。
スーパーで売ってるワインばかり飲んでいます。
普通に美味しいです。
それが私の知ってる「ワイン」の全てだから。
でも考えてみると、
常温で売り場に置かれています。
その時点で既に熱によるダメージを受けていることは確定です。
ピュアな酸は残っていない。
1000円以下のワインはどうでしょうか。
恐らくコスト的にほぼリーファーコンテナ(冷蔵コンテナ)を使っていないでしょう。
ワインの産地の多くは、南半球やヨーロッパです。
それらの船は赤道を通過します。
温度管理をしていないコンテナを使えば50℃は超えるはずです。
たんぱく質に火が入り始めるのは50℃くらいからのようですから、ほぼ煮ているようなものでしょう。
ピュアな味わいなんて残っているわけがありません。
生産もいかにコストパフォーマンスを良くするか、ということが重要でありますから、収量を落として味わいの質を上げようという判断などなかなかできないわけです。
(ちなみにそれらのワインを否定するつもりは毛頭ありません、それも企業努力の賜物だと思っています。)
しかしだからこそ、多くの人にとってワインの味わいは「それ」なんです。
でも「それ」で良いんです。
自分で挽いた豆の味を知らないから。
興味がある人だけが知ればいい、でもできるだけ多くの人に知ってほしい。
じゃあどこに行けば、本当に美味しいワインに出会えるのかというのは、あえて教えるものでもないのかもしれません。
興味がある人はきっと自分で行き着くから。
でもね、スーパーでワインを知って、興味を持った人にはぜひ一度おいしいワインを飲んでみてほしいとも思うんです。
「無い」ものが「ある」。
そして、そこには特大の癒しがあるから。
でもやっぱり少しお高い。
なので、きっとお財布事情的に知らなければよかったって思う人も多いと思うんです。
しかもワインの場合は、管理方法を知らなければせっかく良いワインを買っても台無しになってしまうし。
知らなければ「それ」がワインの味なのに、本当に旨いワインを飲んでしまったら新たな「ワイン」を知ってしまう。
そしてそれはきっとダウングレードできないんです。
ワイン屋をやってると、そういう方を何人も見ます。
でも皆さんどこか満足げなんですよね。
多分本当に美味しいワインで日々満たされているからだと思うんです。
とはいえ、やっぱりコストがかかることなので、安易にオススメはできません。
戻れなくなっても責任は取れないから。
でも一つだけ。
10年ぶりにワイン屋に戻ってきたオイジーだからわかることを一つだけお伝えします。
ワイン好きは出世します。
これは何となくではなく、オイジーの統計です。
これについてはいずれまた記事にできればと思います。
では。
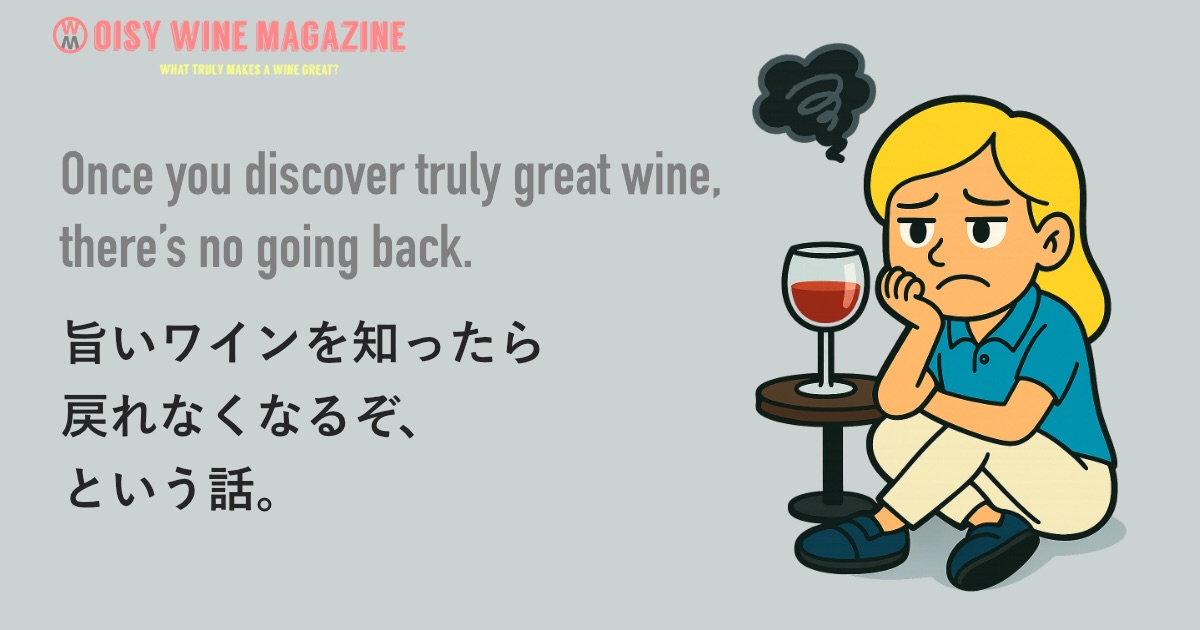

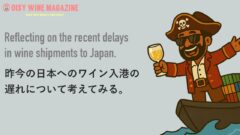

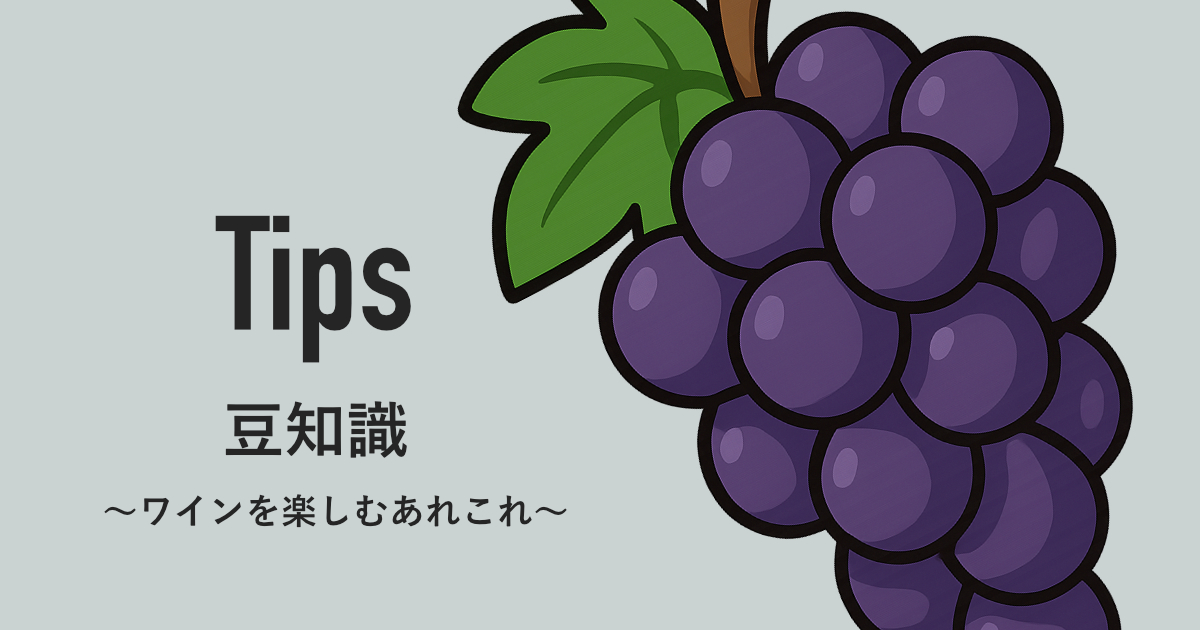
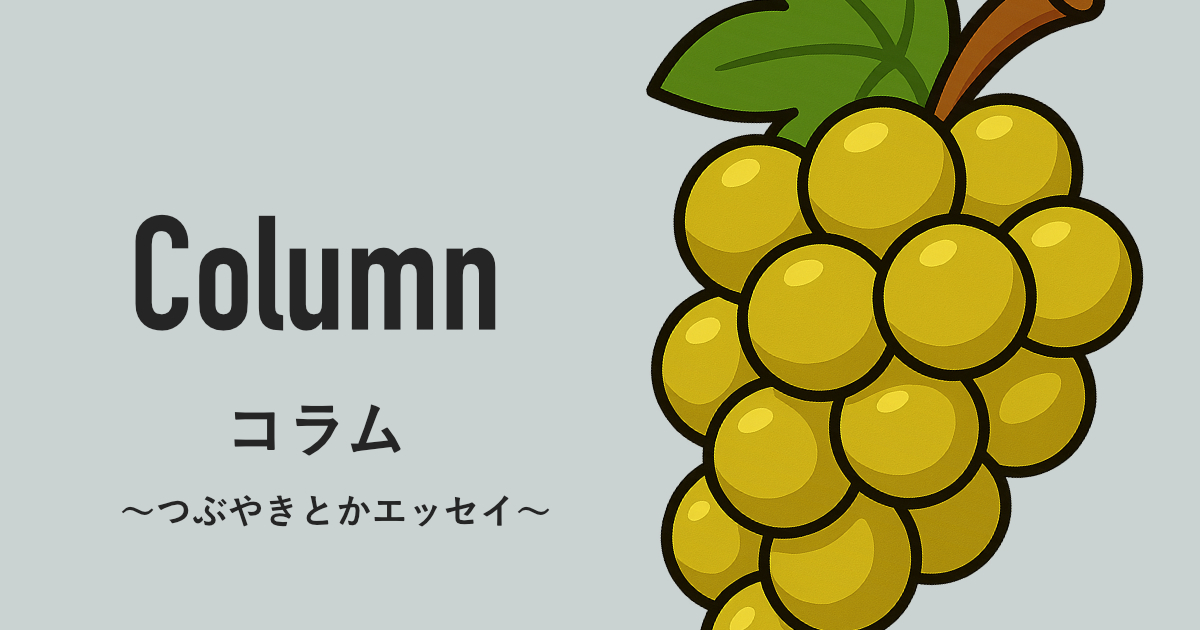


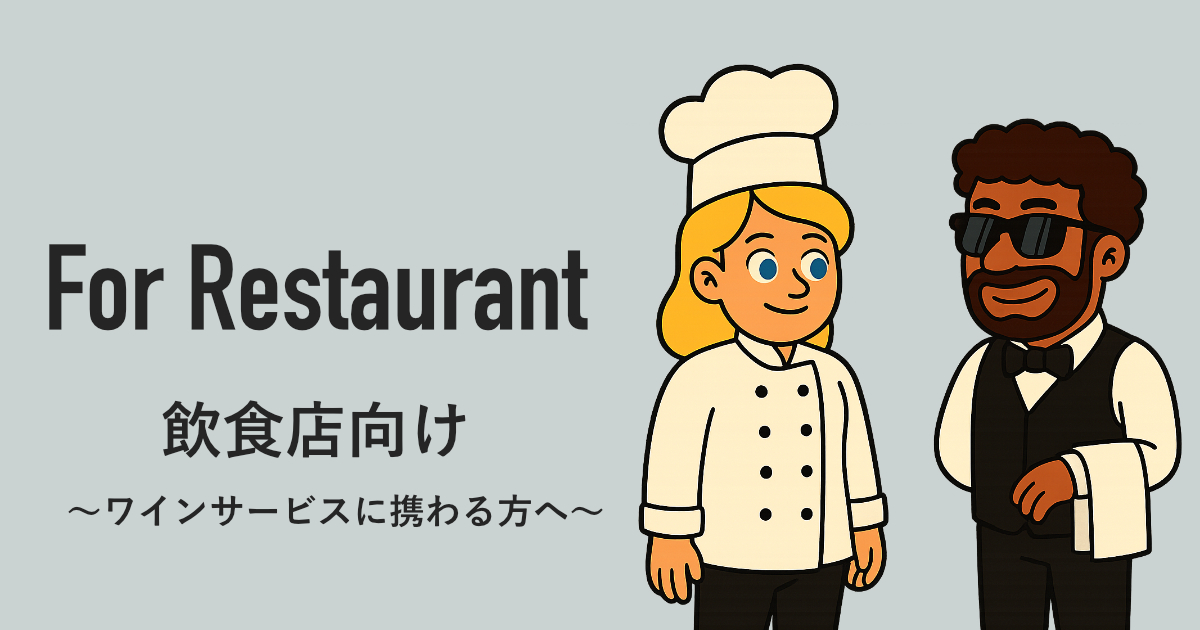


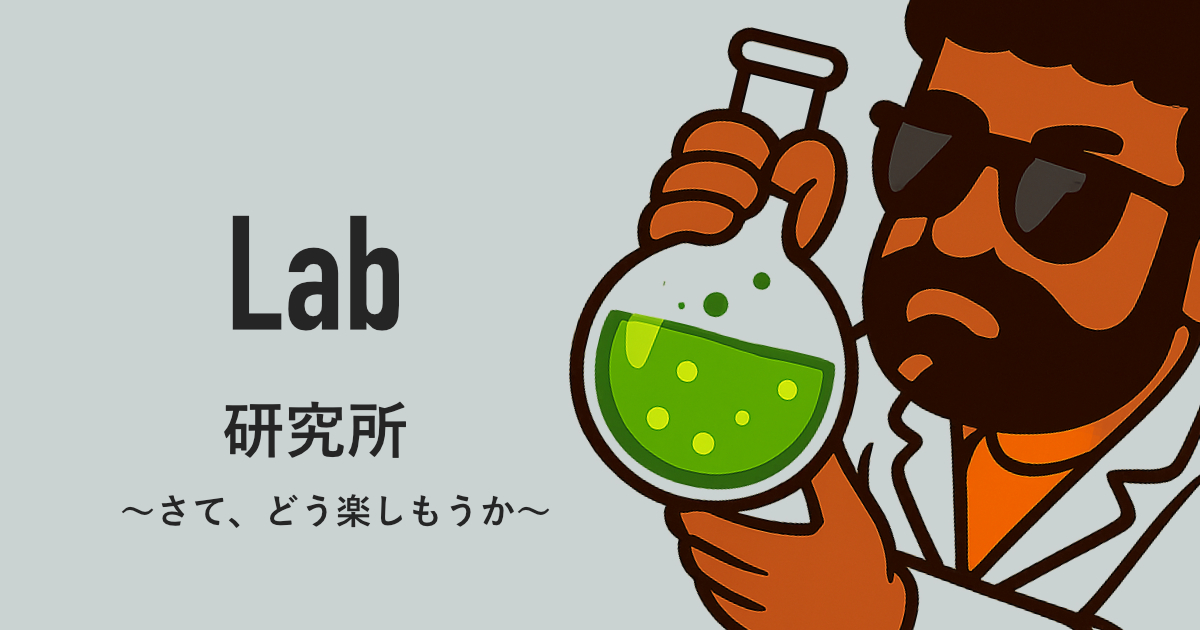





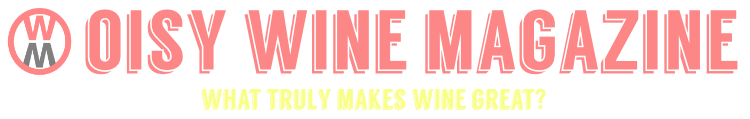
コメント