赤と白の両方を造るフィリップ・パカレが言う、「赤は料理、白はお菓子作り」
赤の造り手であるセシル・トランブレイがいう、「梗は塩、プレスは火加減」
そして今回、白ワインの最高峰の造り手の一人であるユベール・ラミーの「赤ワイン」をテイスティングして思うところがあったので、ツラツラと書き連ねながら、自分の中でバラバラに思いついていることをまとめてみようと思います。
鉄は熱いうちに。
白の造り手の赤ワインに感じる共通点
発端は、メインが白ワインの造り手の赤ワインが、なにか似たようなキャラクターがあり、その要素が造り手を超えて共通していると感じたからです。(良い造り手に限る。)
そしてそれはあまりキャッチーなワインには仕上がらず、どこか閉じ気味で、しかし妙な魅力の片鱗を携えています。
これね、もしかして醸造時の「温度」かな、と思ったんです。
「温度管理」といった方が正しいかもしれません。
料理の世界との対比
かつてレストランで働いているとき、本当にいろんなタイプの料理人を見てきました。
その中で、やっぱり人によって向いている料理のカテゴリーというのがあるんです。
料理人のタイプ分け
- 肉を焼くのが上手い人。
- パスタを造るのが上手い人。
- デザートを造るのが得意な人。
- 前菜を造るのがうまい人。
この中で、1と2は共通していることが多いです、パカレに言わせると赤ワインの醸造。
また、3,4が共通していることも多いです、パカレに言わせると白ワインの醸造。
赤ワイン的な料理と白ワイン的な料理
これの何が違うかって、肉やパスタというのは、火入れをしながら調理していきます。
常に形状変化をしながら手を加えていくわけです。
例えば、油でニンニクを炒めているところに、トマトを入れるなど。
対して、デザートや前菜というのは、調理をしてから火入れをすることが多いです。
例えばスポンジやタルト、テリーヌやパテなどは材料を混ぜ合わせた後にオーブンに入れて火入れをする、という工程です。
性格と向き不向き
ここに大きく性格的な向き、不向きがある、と個人的には考えています。
大雑把な人は1や2が上手いケースが多いんです。
なぜかというと、常に形状変化をしている中で対応していくため、正確性よりも、いかに臨機応変に対応できるか、みたいなところが重要だったりします。
なので、大雑把な人の方が得意というケースが多いのが、個人的な印象です。
3や4というのは、計画的、レシピ通り正確にやることが重要です。
分量が適当だと膨らまなかったり、大きく味わいが外れてしまったりします。
ですので几帳面な人が得意なことが多い。
ここでいう3や4、つまりデザートや前菜造りというのが、今回の白ワイン造りに当たります。
白ワイン醸造における温度管理
そして、デザート造りは、より温度管理がシビアなんです。
チョコレートは適切な温度にすることで、ツヤがあり、口どけが変わります。
ゼラチンは適温で溶かさないと固まらないし、加熱しすぎると凝固力がなくなります。
これは白ワインでも同じなのではないでしょうか・・?
白ワインは果皮を取り除き、果汁の身で発酵させます。
そのため基本的にはタンニンの影響をうけません。
そうすると味わいの中心は酸と果実味とミネラル。
温度管理がより重要になってきます。
温度が低すぎても発酵が始まりません。
しかし高すぎる温度では酸はダメージを受けてしまいます。
酸は白ワインでは味わいの中心、ダメージを受けてしまっては味わいが崩壊してしまいます。
そのため、温度管理には超敏感であることが求められます。
温度の焦点のキャパが狭い。
赤ワイン醸造との違い
しかし赤ワインには果皮由来のタンニンがあり、必ずしも酸が中心ではなくても、味わいを補強する要素があります。
高い温度でないと出てこない要素もあるでしょう、温度の焦点のキャパが広い。
この温度の焦点の違いが、赤の造り手と白の造り手で感覚としてだいぶちがうような気がします。
その結果として、白ワインの造り手は、赤ワインを造るときにも微細な温度コントロールを意識するようになる。
いや、無意識にしてしまうのかもしれません。
その辺の意識の差がワインに現れているように感じます。
白の造り手が赤ワインを造るとき
ここからはさらに推測が加速しますが、白ワインの造り手は赤ワイン醸造でも、温度を低めに管理する傾向がある気がします。
より緻密にコントロールし、赤ワインであっても酸が崩れないように、本能的な意識が向いているようにも感じます。
それが故に、リリース仕立ては特に閉じたような印象になることが多い。
熟成とともに旨味とタッチのやわらかさを上げていくことによって、飲み頃の時期に花開くように設計されていると言ってもいいかもしれない。
このあたりの要素は少し高い温度で醸造されたり、コントロールが甘い方が、熟成せずとも獲得しやすいと思うからです。
しかし、実際には赤ワインの醸造というのは幾分、酸を犠牲にするような温度によってしか獲得できない要素というのもあるような気がします。
そこに抵抗なくアクセスできるのが、赤の造り手。
しかし、白の造り手は本能的に抵抗があり、アクセスできない、もしくはしない味スジを好む、というのが多いような気がします。
それが白の造り手の赤ワインに共通したスタイルを感じる大きな理由の一つかな、と今は思っています。
おわりに
実際にワイン造りしたことがあるわけでもないし、体系的に学んだことがあるわけではありません。
あくまで日々の膨大なテイスティングから産み出された推察です。
これは自分なりの考察であり、まだまだ深められるかもしれませんが、今の段階での結論としてまとめてみました。
間違っていることもあると思いますが、現時点での自分の考えをまとめて、アウトプットして、次の段階に進みたく記事にしてみました。
そのため校正もしていないし、まとまった文章ではなかったかもしれませんがご了承くださいませ。
ではまた。




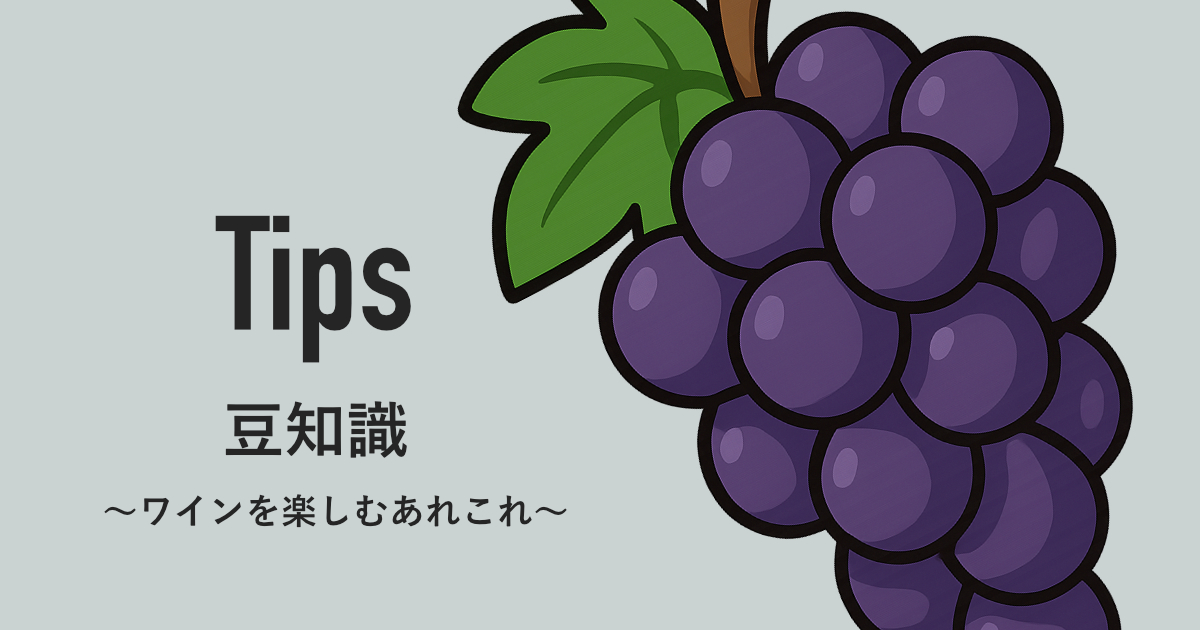
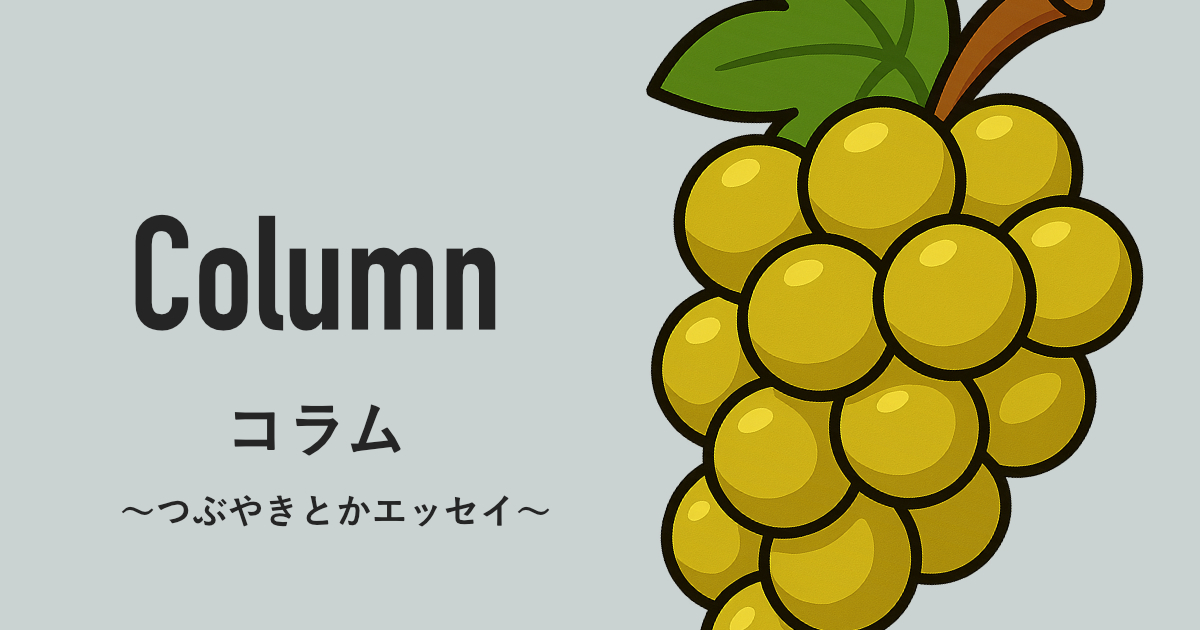


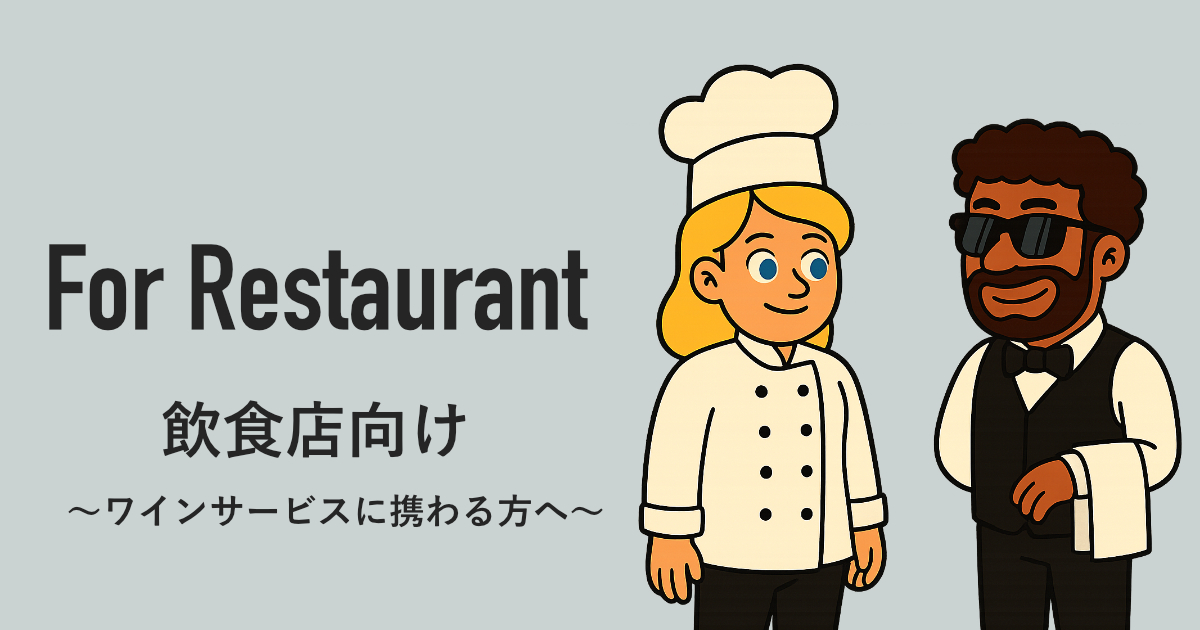


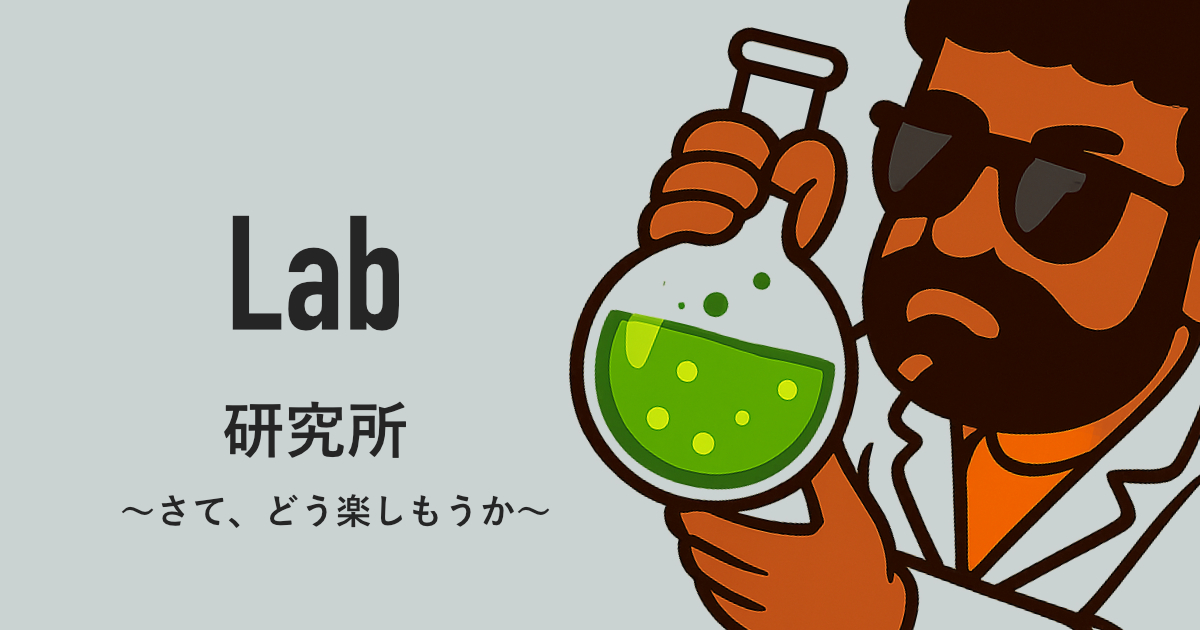





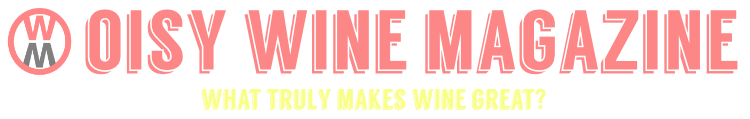
コメント
ものすごく面白いです。
嬉しいコメントありがとうございます!今後もポツポツ更新していくのでまた見に来てください!