こんにちは、オイジーです。
みなさまは“焚き火”の前でワインは飲まれたことはありますか?
先日、ワイン業界の友人と一緒にキャンプをしました。
キャンプで飲むワイン、おいしかったですね~。特に
「夜」
焚火の前で飲むワインは最高でした。
しかし、
「焚火の前で飲むワイン、かなり向き不向きがあるぞ?」
とも思ったので、言語化すべく記事にしてみました。
ワイン好きの方にも、キャンパーの方にも参考になれば幸いです。
焚火の炎が、ワインを開かせてくれる。
これは目から鱗でした。
焚火の炎のじんわりした温かさがワインをいつもより開かせてくれるんです。
いつも
「オンドカンリガダイジ!」
と壊れた機械のように繰り返すオイジーが、そんなこと言ってるの?と思われるかもしれませんが
ダメなのは「温かい場所での保管」です。
「飲みながら温度を上げる」
は、うまくワインを飲むには必須の技術。
とはいえワイン自体が温かく感じるほどまで温めてはやりすぎです。
そしてこの現象、「焚火の炎」だからこそ、「より開かせてくれる」ように感じたんです。
これ焚火の炎の性質を考えると、気のせいじゃないのかもしれません。
「遠赤外線」がワインを開かせてくれたのかもしれない
例えば炭火で焼いたお肉が美味しいのは、火のついた炭から放射される
「遠赤外線」
の効果です。
遠赤外線とは目に見えない、熱として感じる波長であり、物体の表面ではなく、
内部から温める性質があります。
焚火の前に座っていると
「空気が冷たいのに身体の芯が温まる」
と感じるのはこの効果によるものです。
人間の体がそう感じるんです。
ワインがそう感じてもおかしくないでしょう。
実際、遠赤外線は
物質内部の分子の振動(特に水分子)を共鳴的に刺激する
特徴があります。
ワインは水分が主成分なので、
遠赤外線の「水分子の共鳴」は起きやすいといえます。
そしてこの温まり方が他の熱源とは全く違うんです。
たとえば:
・エアコンの熱風 → 空気を温める(乾きやすくムラが出る)
・遠赤外線 → ワインそのものの分子をゆっくり揺らして温める(均一でやさしい)
この“温まり方の質”がポイントで
急激に温度を上げるのではなく、分子レベルでじんわり熱が伝わるので、ワインがショックを受けずに
「自然にじんわり開いていく」
感じになるわけです。
これが室内のエアコンの暖かさとは違った開き方を感じた原因でしょう。
あくまで体感的な印象ですが、理屈としても通じる部分があると感じました。
しかし、これにも向き不向きがあります。
焚火の前で飲みたいワイン
焚火の前で飲むワインを考えるには、
「そこはどういう環境なのか」
を考える必要があります。
夜になり、そこそこ集中できるようになり、繊細なワインもある程度キャッチできるようになりました。
しかし、やはり暖かい。
エレガントで線の細いワイン、酸で飲ませるワインは
「温度の焦点の幅が狭い」
んです。
つまり、暖かくなりすぎるとぼやける。
焚き火前でのワインの温度はコントロールが難しいです。
開いた!と思ってもすぐにその温度帯を通り過ぎてしまう。
なので、もう少し帯域の広いワインが良い。
となるとやはりこれも
「果実味の豊かなワインが良い」
となるわけです。
しっとりとした、果実の広がりのあるワインであれば
ある程度の温度上昇があってもカバーできる懐の広さがありますし、むしろそのくらいがうまかったりします。
具体的には、南仏のラングドック・ルーションやローヌ。ボルドーもいいでしょう。(実際によかったです。)
イタリアなら南のアリアニコやプリミティーボ、北ならヴァルポリチェッラなんかもいいでしょうね。
スペインのテンプラリーニョやガルナッチャなんかもいいと思います。
まとめ
では最後にまとめていきたいと思います。
【”焚火の前”で飲んでおいしいワイン】
・日中よりも、少しエレガントなワイン
(トスカーナのロッソ・ディ・モンタルチーノ、ランゲ・ネッビオーロ、ブルゴーニュの広域など)
・日中よりも、少し複雑なワイン
(ブルゴーニュ、ローヌ、ピエモンテ、トスカーナの中級キュヴェ(村名格))
・”温度の焦点の幅が広い”果実の豊かなワイン
(南仏のグルナッシュ/シラー、ボルドー、タウラージ、アマローネ、スーパータスカン)
おわりに
いかがでしたでしょうか?
焚火の前で飲んでおいしいワイン。
柔らかいワインを、より柔らかくしてくれると感じました。
ちなみに、こちらの記事もおすすめです。
キャンパーでない限り焚火の前で飲む、という環境を整えるのは難しいでしょうが
機会がありましたらぜひ参考にしてみてください。
では、また。






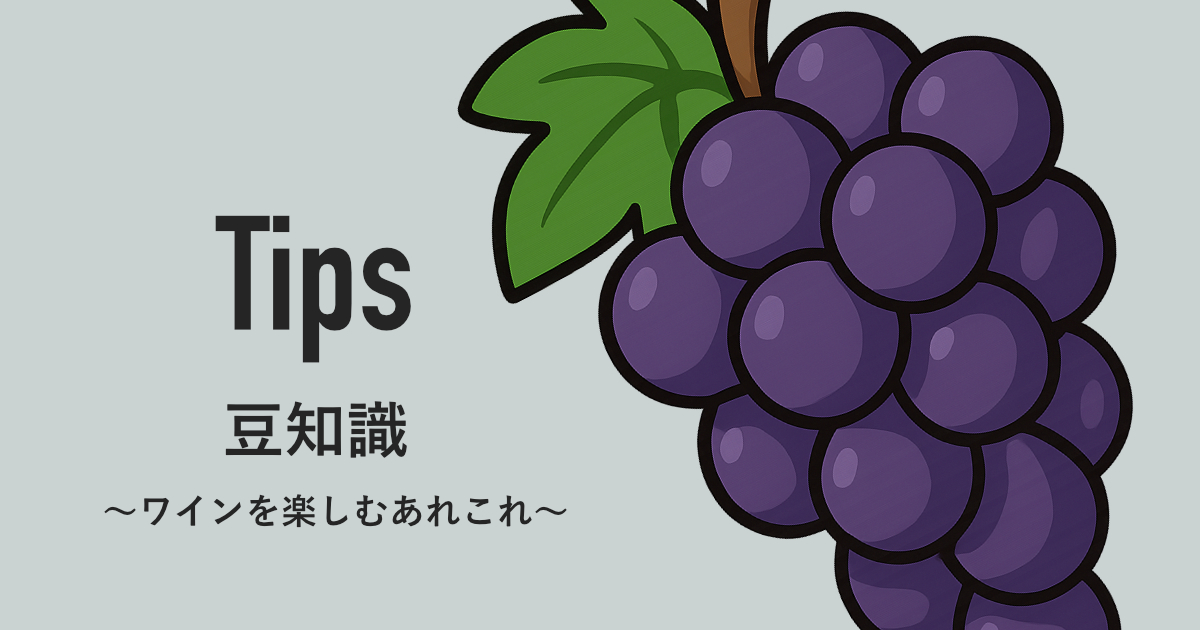
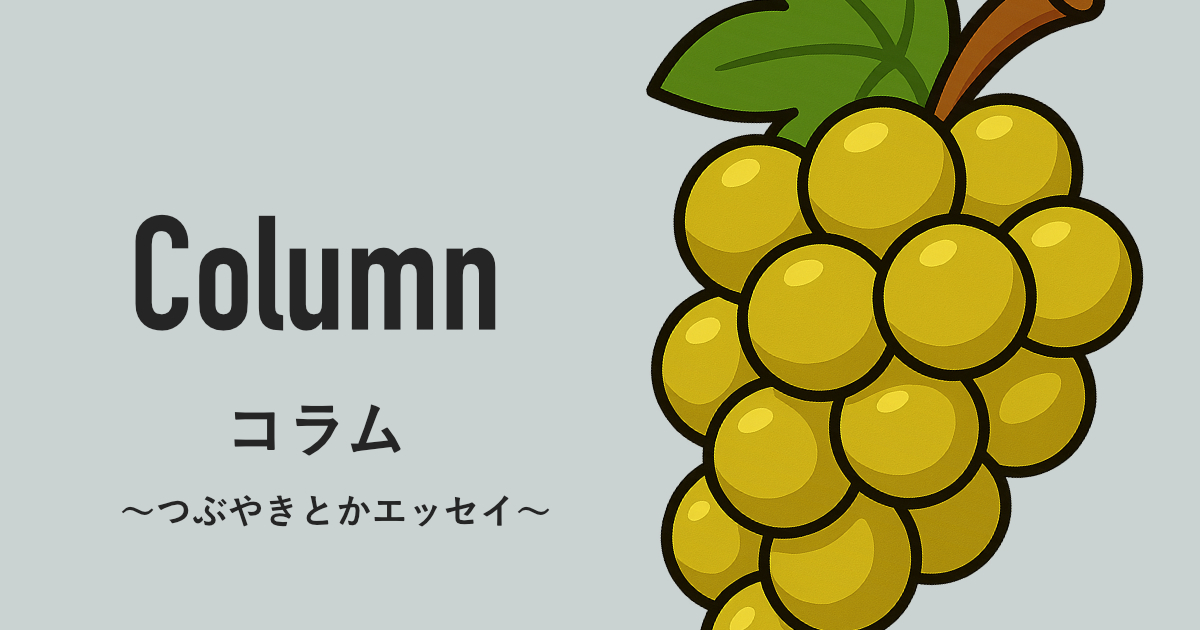


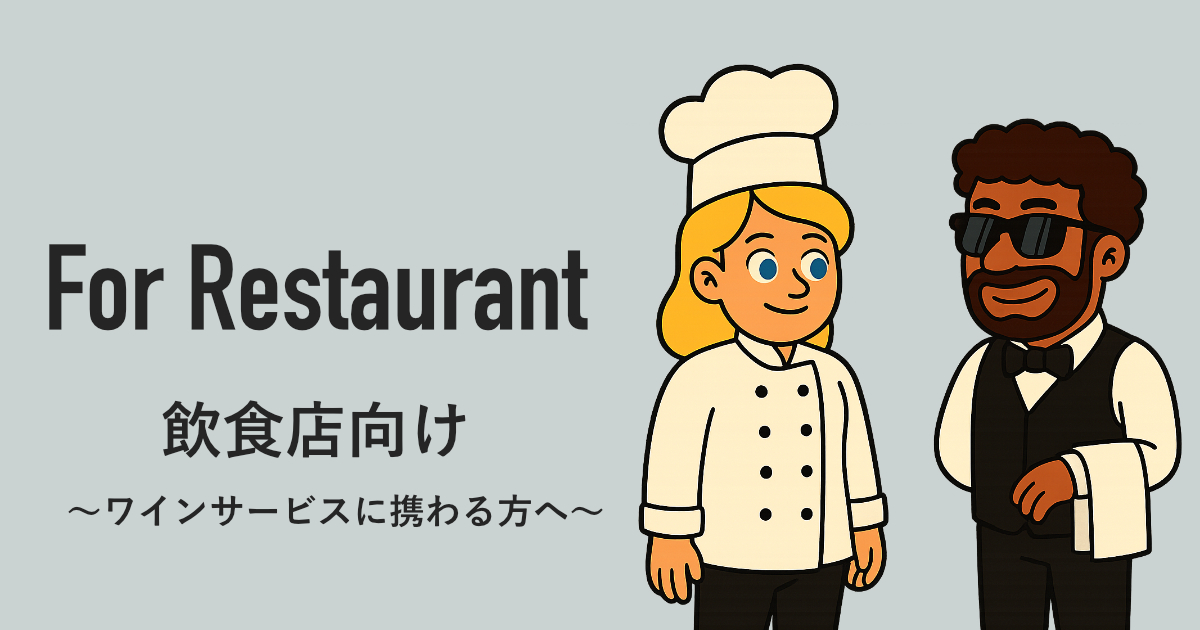


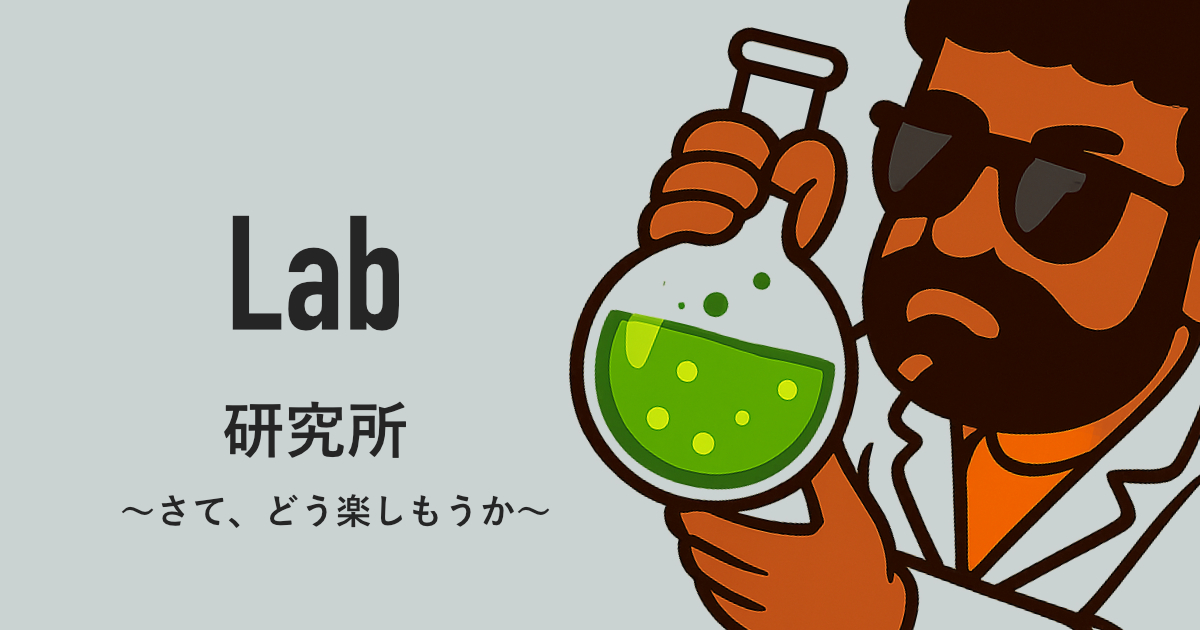





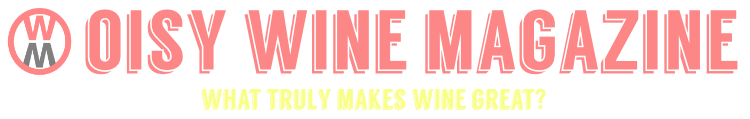
コメント