こんにちは、オイジーです。
今回はちょっと感覚的な話を。
皆様は「ピュアなワイン」はお好きですか?
オイジーは大好きです。
むしろオイジーの選定基準には無くてはならないほど大事な要素、だと思っています。
その大事な大事な、ピュアなワインであるかどうかを見極めるのに必要なのが、
「酸の輪郭」
だと思っています。
今回はこの、いかにも抽象的で、捉えづらい要素について、語っていこうと思います。
- 「アシッド君」のご紹介
- 健康なアシッド君には、ピカピカな「酸の輪郭」がある。
- 健康なアシッド君は、「良質なワインを造る生産者」のワインでのみ生成される。
- 酸へのダメージとはなんなのか?
- 高温に当たると、酸はどんなダメージを受けるのか
- 「潰れた酸」はどうなるの?
- 一度ダメージを受けた酸は「元には戻らない」
- 酸のダメージを回避するには「輸送」や「保管」が最も大事。
- SO2(亜硫酸)はある程度、酸をコーティングする。
- 高温とは何度なのか?
- ワインのタイプ別、保管時の許容温度一覧
- スーパーでは、常温で置かれているから大丈夫なんじゃないの?
- スーパーで売られているワインは、なぜ常温でも一定以上の味わいを担保できるのか?
- なぜスーパーでは、そのような保管状況なのか。
- どこで「酸の輪郭」を保ったワインを買えるのか?
- おわりに
「アシッド君」のご紹介
「酸の輪郭」とは非常に抽象的で、イメージの世界かと思われるかもしれませんが、
確実に「存在する」
とっても重要な要素だと思っています。
科学的にどうなんだ?と言われると・・・正直わかりません。
しかしオイジーがテイスティングで非常に重要視している要素の1つです。
なので、
「あくまで印象でしょ?」
とは簡単に片づけられない議題なんですね。
とはいえ、わかりづらい議題だと思うので、イラスト化して説明してみることにしました。
これが酸のキャラクター「アシッド君」です!

このアシッド君を使って説明していこうと思います。
健康なアシッド君には、ピカピカな「酸の輪郭」がある。
まず大事なのはアシッド君が
健康であるかどうか
です。
健康なアシッド君には、ピカピカな「酸の輪郭」があります。
これだよ!と言葉にするのは難しいのですが、ピカピカでパキパキとした
「酸を覆う膜」
みたいな感覚です。

健康なアシッド君は、「良質なワインを造る生産者」のワインでのみ生成される。
健康なアシッド君はまず、
「良質なワインを造る生産者」
のワインでのみ生成されます。
この記事では、良質なワインを造る生産者についての定義は省きます。長くなるので。
つまり、いまいちな生産者の
アシッド君は健康ではない
ということになります。
ここで言う健康ではない、とは・・・
「既にダメージを受けている」
ということですね。
ではダメージとはなんなのか?
酸へのダメージとはなんなのか?
アシッド君へのダメージとはなんなのか?
これは色々な要素があると思います。醸造上の欠陥だとか。
でもここでは最もダメージの大きい
「酸の天敵」
に絞って解説していこうと思います。
それは
「高温」
です。
高温に当たると、酸はどんなダメージを受けるのか
ではアシッド君は高温に当たると、どんなダメージを受けるのでしょうか?
これまた感覚的な話になるのですが、
「潰れる」
という表現が最も適切かと思います。
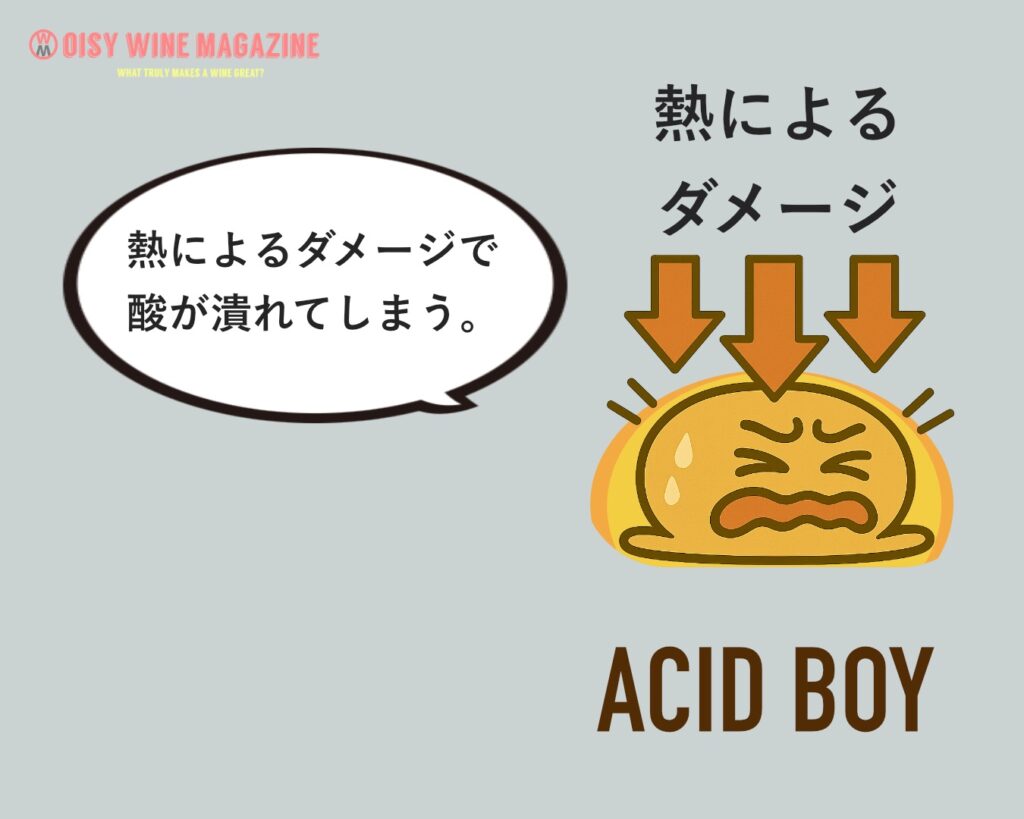
「潰れた酸」はどうなるの?
では、「潰れた酸」はどうなるのでしょうか?
結論は…
「ピュアな質感を失ってしまう」
わけです。
ピュアな質感を失うと、
味わいにハリはなくなり、
抑揚もなくなります。
結果として
「ぼやけた味わい」
になり、いまいち焦点の合わない凡庸なワインになってしまいます。
一度ダメージを受けた酸は「元には戻らない」
そして一度ダメージを受けた酸は、
「元には戻らない」
んです。
一度火が入った茹で卵は、生卵に戻りませんよね?
熱中症でダメージを受けた脳や内臓も元には戻らないと言います。
それと同じで、高温でダメージを受けた酸も、元には戻らないんです。
酸のダメージを回避するには「輸送」や「保管」が最も大事。
高温に弱い酸は、ダメージを回避する必要があります。
では、どこでそのダメージを最も受けやすいのでしょうか。
ズバリ、答えは・・・
「輸送」や「保管」です。
これが最も大事です。
これ実はよくあるパターンなのですが、
「生産者から出荷した時点ではダメージを全く受けていない」
のに、
「輸送や保管でダメージを受けている」
というのはよくあるパターンなんです。

とくに気を付けなければいけないのが、夏場の持ち運びです。
どう持ち運べばいい加減にわからない・・・という方はぜひ、こちらの記事もご参考ください。
生産者からしたらせっかく美味しく造っているのに、運ぶうちに不味くされてしまったらたまったもんじゃないですよね。
SO2(亜硫酸)はある程度、酸をコーティングする。
これもあくまでイメージの話です。
SO2や亜硫酸などの酸化防止剤は、ある程度、酸をコーティングするような機能がある。
と個人的には思っています。
しかし、同時に味わいを「カチッ」とさせてしまい、質感のディテールや抑揚までも抑えてしまう機能があるとも感じています。
しかしこれは使用する量や、熟成期間の問題でもあるとも考えており、その使用する加減に生産者のセンスが問われる、と考えています。
使用量が少なければ、質感や抑揚はそこまで抑えられませんし、
使用量が多くても、長い熟成期間とともに質感や抑揚が出てくるケースもある
と考えています。
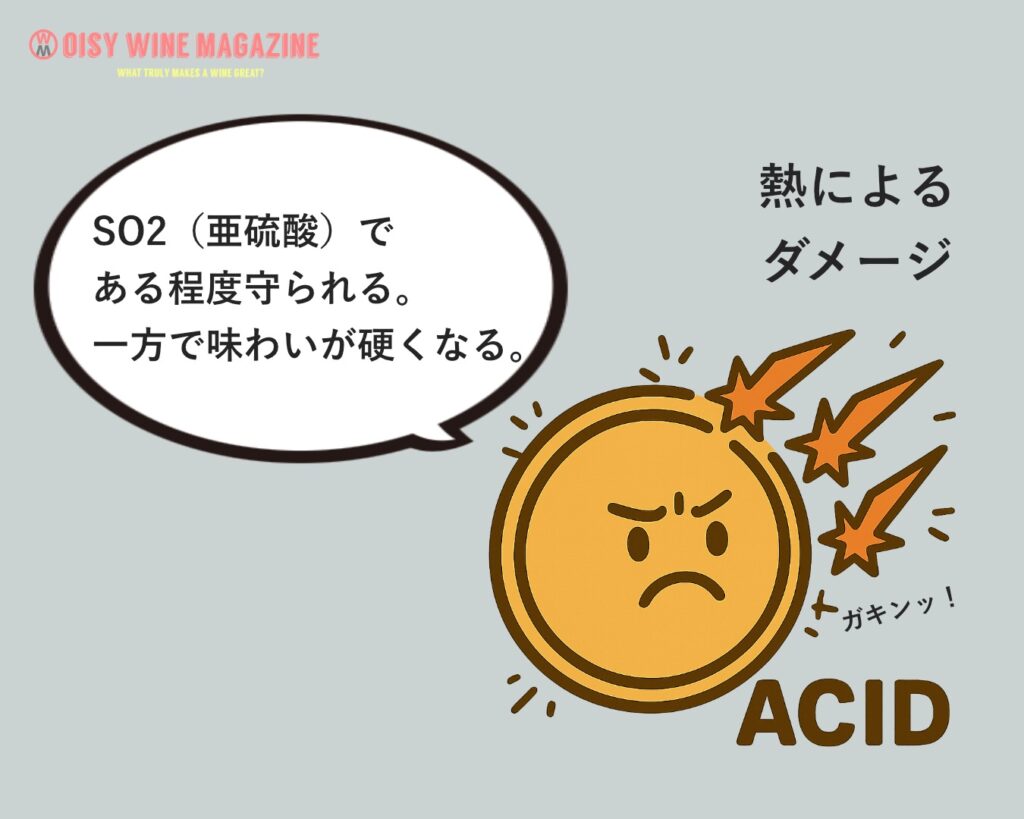
高温とは何度なのか?
ではダメージを受ける温度とは何度なんでしょうか?
これも一概に言えない・・・と考えています。
先に申し上げた通り、酸化防止剤の使用量の違いや、産地などのワインが持つ特徴によって違うと考えているからです。
とはいえ、全くの指標が無いのもどうなの・・・?と思いますので、オイジーが考える、タイプ別のワインの温度の許容範囲をまとめてみようと思います。
温度に関してはまだ研究中の部分もあるので、参考程度にご覧ください。
また今後の研究次第では変わる可能性もあります。
ワインのタイプ別、保管時の許容温度一覧
| 保管温度帯 | ワインへの影響 |
|---|---|
| ~12℃ | 白ワインやスパークリングワインを一時的に冷やしておく温度。長期的にこの温度帯で保管すると低温劣化する。 |
| 12~14℃ | ナチュラルワインの、SO2を全く添加していないもの。 一方で一般的なワインを12℃付近で保管すると熟成の速度が遅くなる。 |
| 13~14℃ | ナチュラルワインのごく少量SO2を添加しているもの。 または冷涼な産地のもの。 迷ったらこの温度帯での保管を推奨。 |
| 13~16℃ | 暖かい産地のもの、酸より凝縮感やボディで飲ませ、かつSO2をそれなりに添加しているもの。 13℃付近だと熟成は緩やかに進み、16℃付近だと熟成は加速する。 一方で16℃付近だとSO2の添加がないもの、ごく微量のみのものは再発酵や熱によるダメージなども起こりえる。 |
| 17℃~ | 一部のワインは耐えられるが、基本的にダメージを受ける温度。SO2をしっかり添加されているワインでも、ダメージを受ける可能性がある。 |
ちなみに、温度はワインの熟成とも密接に結びついており、高いと熟成が早く進み、低いと熟成がゆっくり進むというのは、体験をもって確信しております。
また、温度管理には単に「酸」のみではなく、他の要素も関連してきます。
例えばSO2を使わないナチュラルワインであれば、温度の上昇とともに停止していただけの酵母や乳酸菌が再び活動をはじめ、再度アルコール発酵やマロラクティック発酵を始めるという可能性も出てくる、というケースもあり得ます。
なので、保管温度帯というのはワインのスタイルによって最適なものは違う、と考えています。
上記の温度帯は、一応これらのリスクも加味した指標となっています。
スーパーでは、常温で置かれているから大丈夫なんじゃないの?
これはよく抱く疑問です。
スーパーや食料品店では、常温で置かれているから大丈夫なんじゃないの?
というご指摘。
これはズバリ
「ダメージを受けたワインを売っている」
に過ぎません。
「え、でもスーパーで買ったワインもおいしかったよ?」
と思われるかもしれません。
でもワイン屋としてこれだけは言わせてください。
「本当はもっとおいしかったはず」
なんです。
スーパーで売られているワインは、なぜ常温でも一定以上の味わいを担保できるのか?
本当はもっと美味しいとは言え、スーパーで売られているワインもそれなりにおいしく飲めます。
ではなぜスーパーで売られているワインは、常温でも一定以上の味わいを担保できるのか?
これの
「安定化処理(清澄・濾過・酸化防止剤を使った殺菌的瓶詰め)を行っているから」
なんですね。
しかし前述したようにこれらの処理は往々にして、味わいの抑揚や、質感のディテールは覆われてしまうことが多いんです。
でもこれらの処理が悪いわけではありません。
むしろ熱に晒されても一定以上の味わいを担保できるという意味では素晴らしい技術です。
しかしこれらの処理をしたとしても、全てのダメージを撥ね退けることはできないんです。
ワインの性能に頼って、温度管理を疎かにした結果が、ぼやけた味わいになるんです。
でもそれが多くの人がイメージするワインの味わい。
つまり
「酸の輪郭が潰れたワイン」
なんです・・!
本当に旨いワインはもっとおいしい・・
そう
「酸の輪郭があるワイン」
はとってもおいしいのです!
その中でもさらに良質なものは、癒しや感動までもを、もたらしてくれます。
それをもっとたくさんの人に知ってほしいんです。
なぜスーパーでは、そのような保管状況なのか。
ではなぜスーパーではそのような保管状況なのでしょうか?
前職で様々なスーパーに出入りしていたオイジーには分かります。
それは
「ワインの専門家がいない」
からです。
また、単に専門家と言っても、ただ資格を持っている人、ではありません。
ワインの資格試験にはこの温度問題はそこまで大きく触れられていないのです。
残念ながら、ワインの資格を持っていても、ダメージを受けた状態のワインが普通だと思っている人が大勢います。
ちゃんと日々テイスティングをして、ワインの味わいのなんたるかを理解しようとしている人間は稀なんです。
むしろ本当においしいワインを飲まれる愛好家の方ほど、温度管理には敏感で、注意を払っています。
自腹を切って買ったワインは、誰だっておいしく飲みたい・・・ですからね。
オイジーは可能な限りその想いに応えたいし、生産者の努力も余すことなく伝えたいんです。
どこで「酸の輪郭」を保ったワインを買えるのか?
では、どこで「酸の輪郭」を保ったワインを買えるのでしょうか?
それはもう、
「ワインの扱いをわかっている専門店」
に限ります。
専門店の中にも、温度管理をしていないお店はたくさんあります。
理想は14℃以下です。
ナチュラルワインの造り手には「14℃以下で保存」を明記している造り手もいます。
わかりやすい感覚としては、
お店のセラーに入った時に
「半袖で長時間過ごすのはキツイ」
と感じるレベルです。
またあまり知られていませんが、
「日光に当たらないように保管されている」
もすごく大事です。
ここでは詳しく書きませんが、
紫外線もワインにダメージを与えます。
これは守られていないワイン専門店は非常に多いですが、温度管理に引けを取らないくらいワインにダメージを与えます。
まとめますと、
①14℃以下で保存されている。
②日光が当たらないように保管されている。
この二点をしっかり守っているお店で買うことを強くオススメします。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
途中「酸の輪郭」から逸脱してしまった部分もあるかもしれませんが、オイジー的には非常に大事な要素だったので記事にしてみました。
ちょっと何言ってるかわからなかった、という方もいるかもしれませんが
一人でも多くの方が
本当においしいワインに巡り合えるように、この記事を書きました。
お役に立てれば嬉しいです。
ではまた。
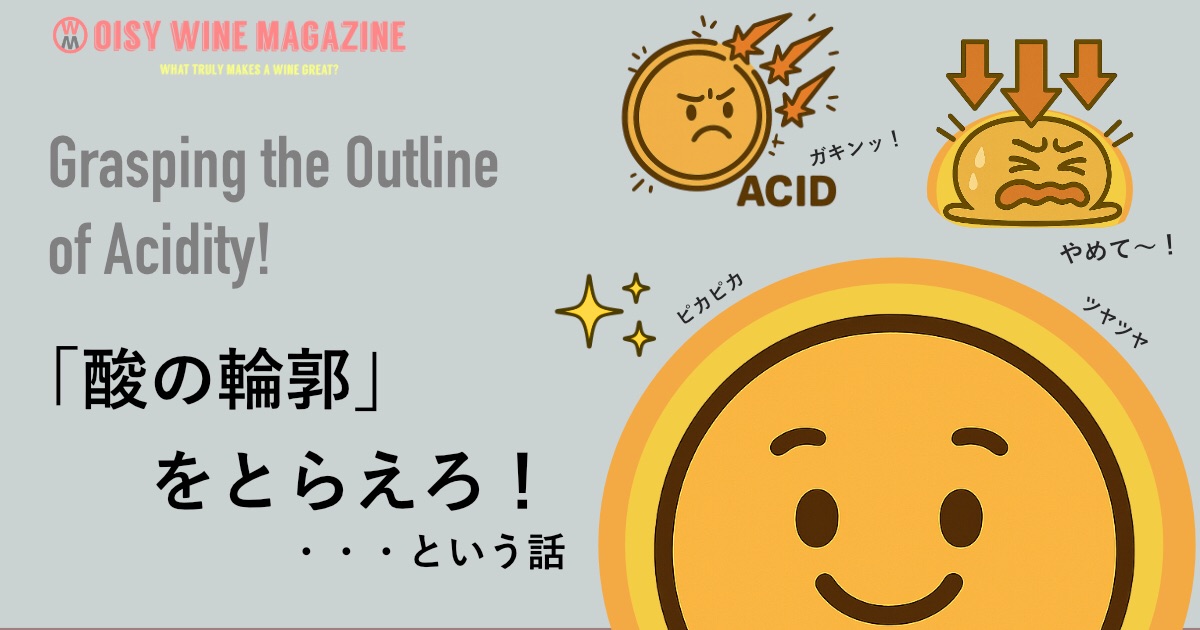




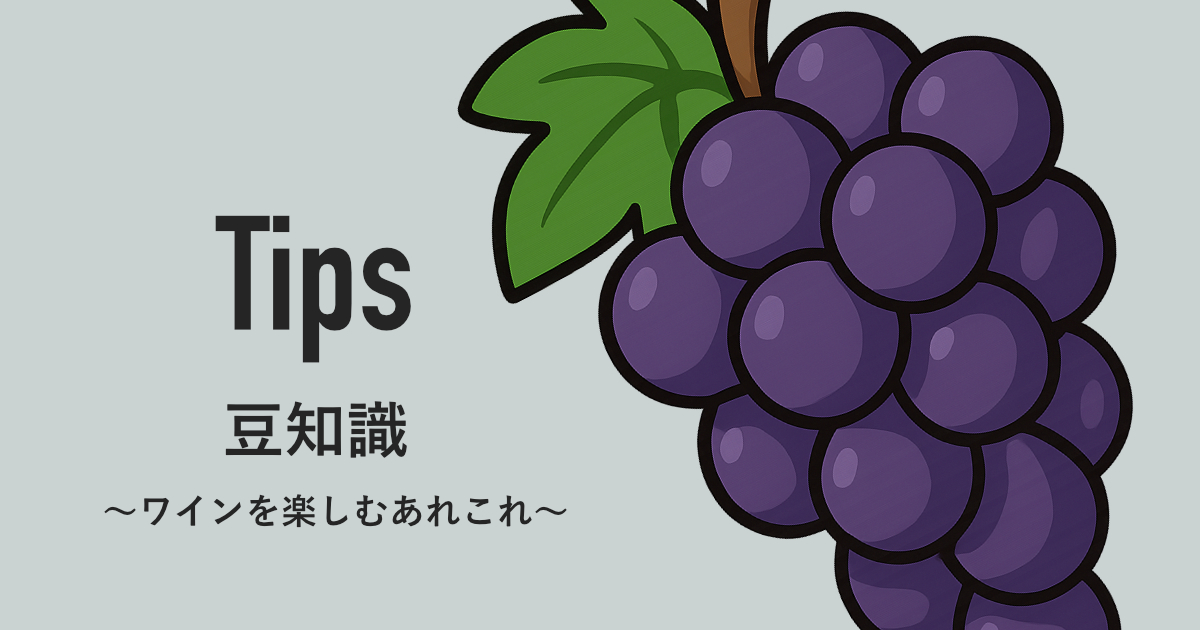
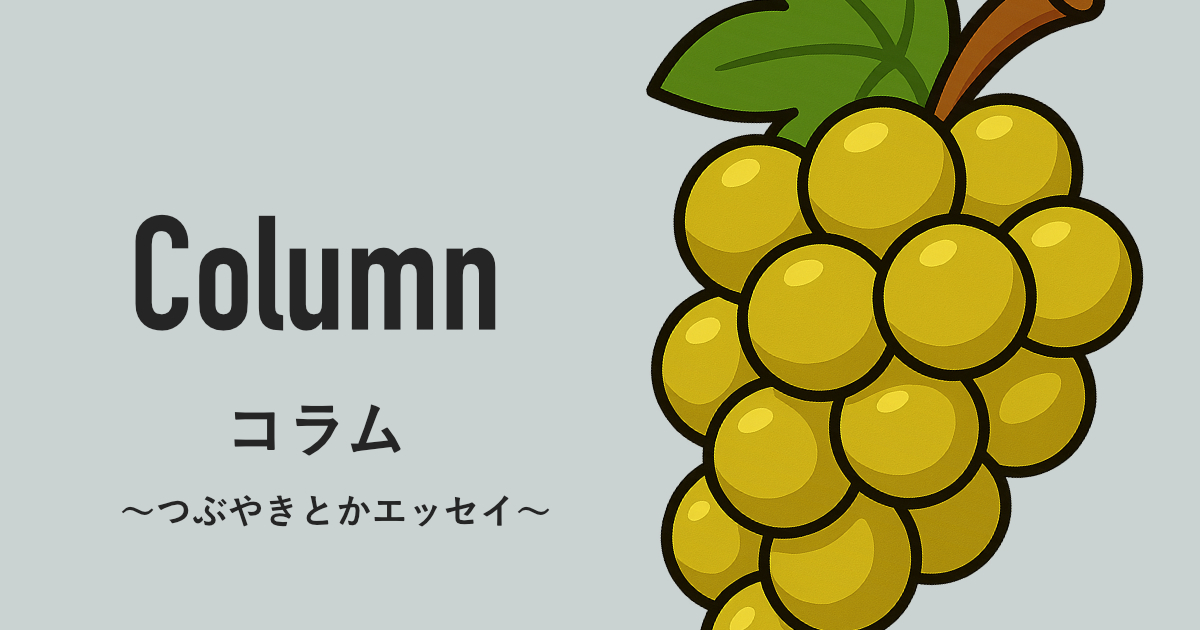


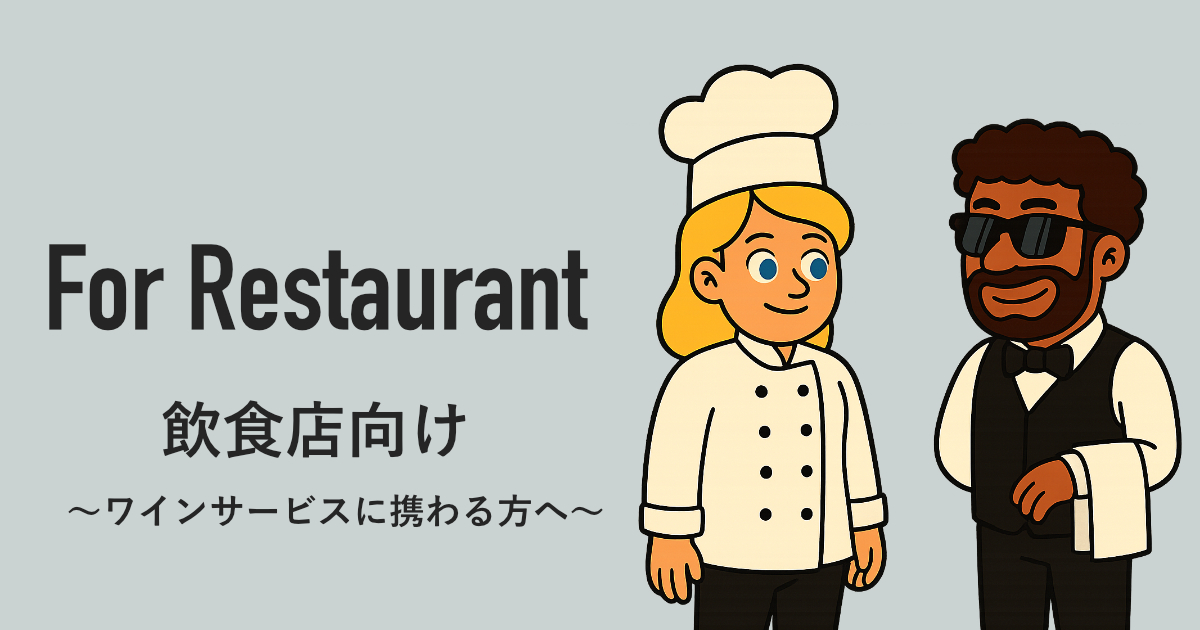


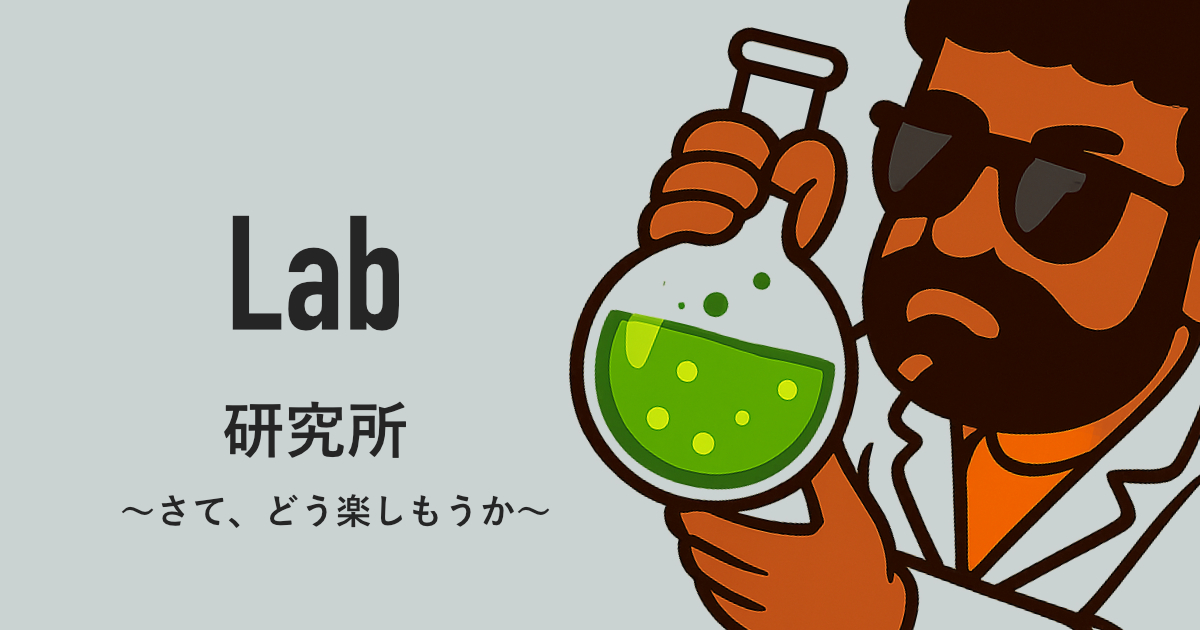





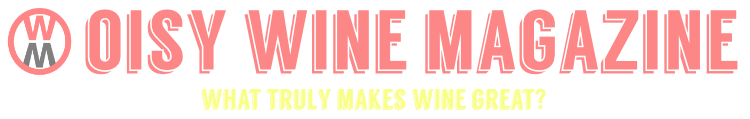
コメント