こんにちは、オイジーです。
2025年現在、日本はインフレ真っ只中です。
美味しいワインをより安く探したい
と思っても、徐々にその選択肢は狭まる一方。
じゃあどうすればいいのか?
オイジー的には一つの手段が
「歴史のあるワイナリーを狙え」
ということです。
何言ってんだと思われるかもしれませんが、これには「明確な理由」があるんです。
ナチュラルワインの大半は新興ワイナリー
今をときめくナチュラルワイン。
ピュアで、キャッチーで確かに旨いです。
しかしただその大半は新興ワイナリー。
ワインを作るにはタンクや瓶詰めの機械、熟成用の樽など様々なコストがかかります。
そのコストをまずは回収しないといけません。
つまりそのコストは液体に乗ってくるわけです。
減価償却などの真っ最中ですから、そのコストは大きく、何年もかかるでしょう。
歴史のあるワイナリーは減価償却が終了している
対して老舗の造り手は既に減価償却も終了し、
設備費がコストを圧迫しない。
さらに新樽を使わない造り手なんかはなおさらで、樽を50年使い回す猛者もいると聞きます。
そういう造り手は樽コストがほぼゼロ化しているわけです。
しかも販売のサイクルが出来上がっていれば、熟成したものを蔵出ししてくれることもあるからすぐに旨い。
イタリアの老舗ワイナリーなんかは5年、10年寝かして出荷してくることもざらにあります。
もちろん修繕費や買い替えなどの維持費もかかるわけで、必ず老舗ワイナリーがコスパ良いという訳ではありませんが、
実感できるほどの価格差があるのは、間違いない事実です。
歴史のあるワイナリーは生産量が多い
歴史のあるワイナリーは生産量がそこそこ多い。
周りの生産者が辞めて、畑を引き継いでほしいという依頼もあるだろうし、
畑を買って増やしてきたり
はたまた開墾したり。
なにかと「生産量が少ない」ということがフォーカスされやすいワイン業界ですが
「生産量を増やしてきた」ということは
スケールメリットを享受できるわけで
瓶やコルク、梱包資材の段ボールなどの仕入れコストもかなり違うはずです。
確かに安易なシステム化で味を落とすケースも散見されますが、
基本は顧客サービスの向上を目指した取り組みであるはず。
「製品がちゃんと行き渡っているから、過剰な値上がりがしない」
は、むしろ本来の顧客視点にたった素晴らしい取り組みであるはず。
ワインはその希少価値から値上がりするのが常ですが、
買いやすいワインだから美味しくないわけではない
ということではないという視点は忘れずに持っておきたいですね。
顧客に支持され続けているから、続いている。
そして禅問答のようですが
「歴史のあるワイナリーは、なぜ歴史があるのか?」
その答えは、
「長く続いている」
から。
では、なぜ長く続いているのか?
といえば
「顧客に支持され続けている」
からなんですよね。
そして、なぜ顧客に支持され続けているのか?
といえば
「旨いから」
な訳です。
そしてここで大事なのは
「人は価格以上に価値のあるものを求める」
ということで、常に
「お値段以上」
のワインを造り続けてきたからこそ続いているのだと思います。
ブドウというのは農作物です。
毎年毎年、質の高いブドウを作るというのは並大抵のことではありません。
それを
「続けてきた」
というリスペクトは常に持って接したいものですね。
では、また。




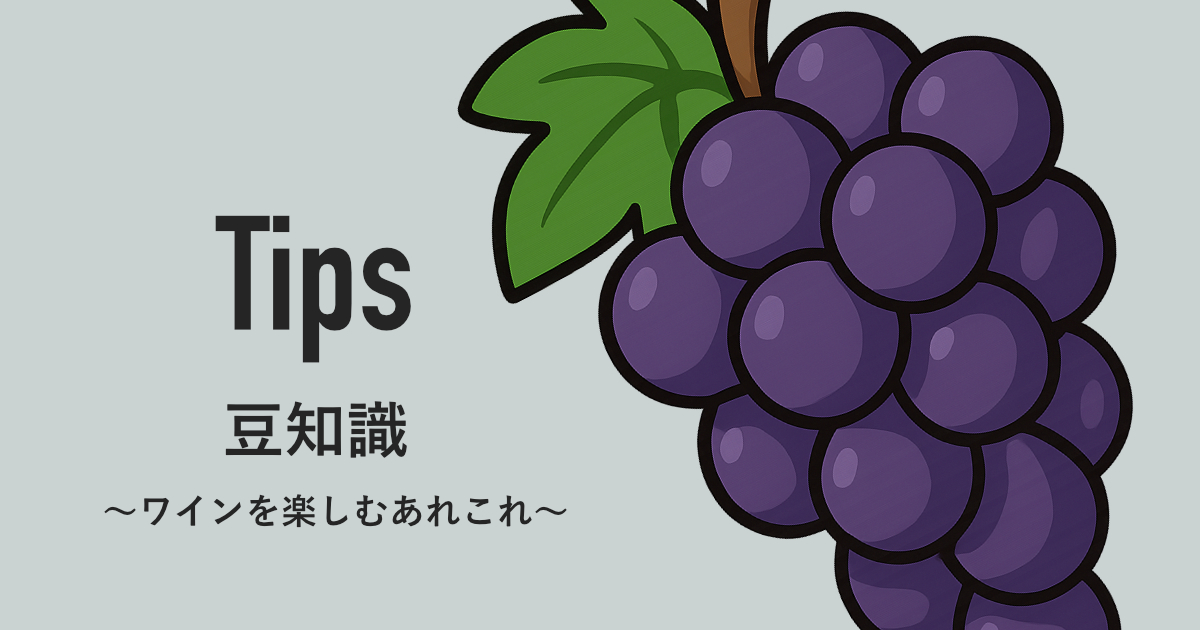
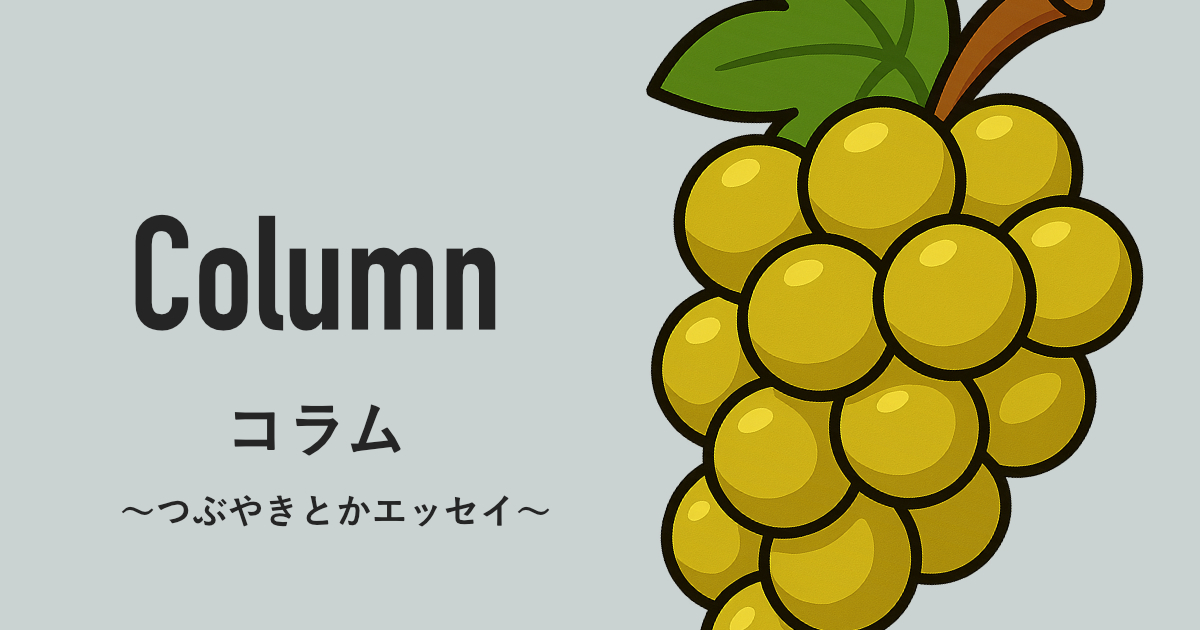


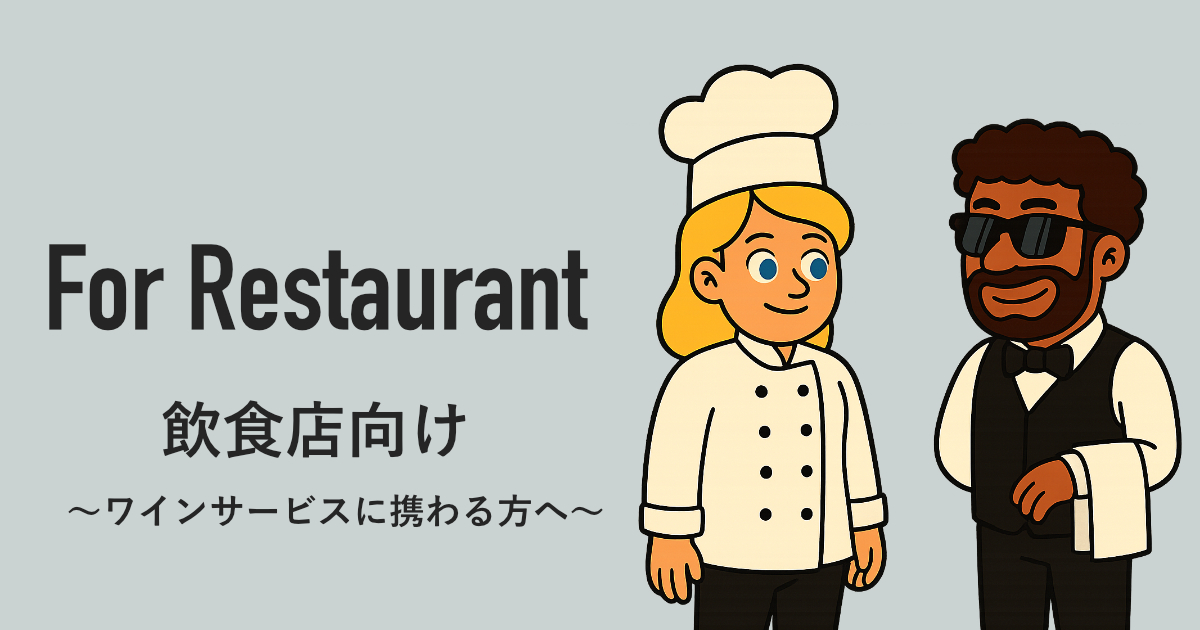


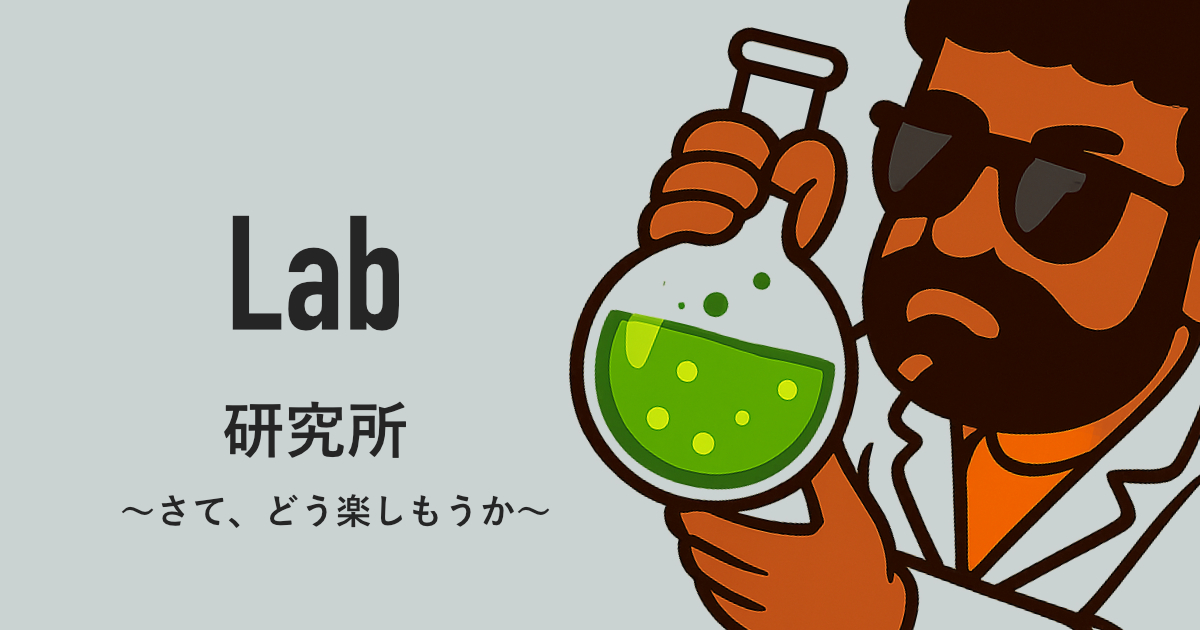





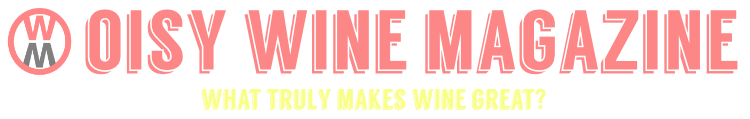
コメント