どうもこんにちはオイジーです。
今回はワイン初心者に向けた記事を一つ。
先日、
・ワイン初心者の友人
・ワイン業界で長いこと働く友人
・オイジー
の3人で飲んだのですが、
そこでちょっとした気づきを得たので記事にしてみました。
それが、ワイン初心者が知らずにぶち当たってる
「酸の壁」
です。
ワイン初心者は、ワイン上級者の感想がわからない。
ワイン初心者の方で
「ワイン上級者の言っている味がわからない」
と思ったご経験はありませんですか?
思い返せば、オイジーはよくありました。
そのわからない部分が、ワインをミステリアスな飲み物だと思わせていたのかもしれません。
で、今回一緒に飲んだワイン初心者の友人も同じように言っていたんですね。
ワインが酸っぱい
その場では皆同じワインを飲んでいました。
オイジーと、ワイン業界の友人がとある白ワインを飲んで、
「オイリーでいいね」
とか
「果実味がしっかりあるね」
とか
「○○の香りが良いね」
とかそんな話をしていました。
しかし、ワイン初心者の友人の感想は
「酸っぱいワインだ」
でした。
もしや我々は「酸」に「慣れ過ぎ」ている…?
今度はそれを聞いた、ワイン業界で長いこと働く友人がこう言ったんですね。
「まあ僕らは酸に慣れてるからね。」
・・・
「僕らは”酸”に慣れている…?」
普段なら右から左へ聞き流してしまうその言葉が、妙に気になり、脳裏に反響していました。
そして、この日のオイジーは憑りつかれたかのように考え込んでしまいました。
なぜなら、ここに
ワインを長いこと飲んでいる人と、
ワインを飲み始めたばかりの人の
「差」が詰まっていると思ったからです。
つまりワイン初心者から見た時の最初の壁が
「酸への慣れ」なのではないかと。
酸に慣れると…?
全てとは言いませんが、大半の方がワインを飲んでいくと徐々に
「酸のあるワインを求めるようになっていく」
んですね。
これは日々接するお客様の傾向の中から拾い上げたオイジー統計に過ぎませんが、内容としては信頼できるレベルだと思っています。
なぜか?
やはりこれは
大小あれどワインを飲み続けるうちに
「酸との接触」
を繰り返すことによって、徐々に
「酸に慣れる」
それがさらに加速し、やがて
「酸が物足りなくなる」
のではないのかということです。
また同時に
「野暮ったいワインが飲みたくない」
というご意見を持たれる方が多くなります。
これはつまりどういうことかというと
「酸の少ないワイン」が
「緩く感じられる」ことを
「野暮ったいワイン」と表現しており、
徐々にそのようなワインが受け付けなくなっていくんですね。
その結果、
「酸のあるワインを求める」
という方向に進む方が多くなっているように感じます。
初心者の感覚は、まだ情報が少ないということを留意しなければならない
対してまだ飲み始めたばかりの方は
「濃いワインが飲みたい」
とおっしゃられることが多いわけですが、
よくよく話を聞いてみるとそれは、ワイン好き玄人が想像するような、
「凝縮した重たいワイン」
というわけではなく、
「酸が緩く、果実味に富んだワイン」
のことであるケースが散見されます。
これはどういうことかというと
経験が浅いということは、
「知っている味わいの幅も狭い」
ということでして、
あくまでその
「知っている範囲での濃さの感覚」
になるわけです。
多くの初心者が高くても手を出すワインの価格帯は2,000~3,000円くらいだと思います。
「本当の濃さ」
を表現するには、収量を何分の一にも落とさなければいけないわけで、
その味わいはこの価格帯では到底辿りつけないわけです。
でも「濃いワインが好き」というにはなにかしらの経験があるわけで、
ではなにをもって「濃い」と感じているのかといえば
実は「酸のゆるさ」と「果実味」に由来するというケースが多いんです。
酸に慣れると、隠れていた要素が見えてくる
話を戻しまして、徐々に「酸に慣れる」とどのような現象が起こるかというと、
「今まで酸に隠れていた要素が、見えるようになってくる」
わけです。
要は酸が強いと、まず
「酸っぱい」
と感じるわけです。
頭の中はこの「酸っぱいが支配的」になり、次のステップになかなか進みません。
しかし酸に慣れてくるとこの「酸っぱい」を自然と受け止められるようになってくる、つまり
「スルースキルが身につく」
ようになってきます。
そうすると
「酸に隠れていた要素に、意識が向けられる」
ようになり
「酸の奥にある要素を味わえる」
ようになるわけです。
例えばレモンをかじると酸っぱいですよね?
でも二度目にかじろうとすると、最初よりも酸に慣れているから、酸の奥にある「酸の甘さ」を感じることができた。
というご経験はございませんか?
これと同じことなんです。
つまり「酸に慣れる」ことがワイン初心者にとって
「最初の壁」
なんです。
「酸の壁」を乗り越えるには?
ではこの最初の
「酸の壁」
を超えるにはどうすればいいか、
ということですが、オイジー流の方法をお伝えいたします。
①…「手広く飲む」
②…「自分の好きな産地を見つけて飲む」
③…「少しずつエリアを広げていく」
このような手順です。
単純に「酸の強い、北の産地のワインばかり飲めばいい」かといえばそうではないと思うんですよね。
一つずつ解説していきます。
①…手広く飲む
まずは「手広く飲む」ですね。
これはまあ言われなくても色んな人が通る道だとは思います。
現代ではワイン産地は世界中に広がっています。
で、酸のレベルというのは産地によって変わります。
できるだけ色んな産地のワインを飲んで、まずはワインの世界の広さを体験してみてください。
最初はラベルが可愛かった、この国が好きだから飲んでみた、そんな感じの選び方で構いません。
なぜならこの目的は
②の「自分の好きな産地を見つけて飲む」
のためだからです。
②…「自分の好きな産地を見つけて飲む」
手広く飲んでいるうちに少しずつ自分の好みがわかってくると思います。
そうなったらもうこっちのものです。
産地によってワインのキャラクターは似てくるので、好きな産地が見つかったら重点的にその地域のワインを飲んでみてください。
現時点で「そこ」が
「あなたの”酸”のレベルの適正地」
です。
「おいしい」
と感じられる自分の酸のレベルにあったワインを見つけてください。
そして、そのワインの産地をチェックします。
この産地は、あなたの酸のレベルに合っているはずなので、
「酸の向こう側の味わい」が拾いやすいはずです。
具体的には
「質感」や「舌触り」、「甘みはあるかないか」「果実味」「濃縮度」「深み」「奥行き」「エキス感」「広がり」「伸び」
などです。
これらをチェックしていき、自分の好みを把握していきます。
そして③に繋がります。
③…「少しずつエリアを広げていく」
しらみつぶしでも、決め打ちでも良いです。
好みのエリアを発見したら、徐々にそのエリアを中心に、広げていきます。
一般的には、
北半球では北に行くほど酸が強くなります。
反対に
南半球では南に行くほど酸が強くなります。
要は「赤道から離れるほど酸が強くなる」わけですね。
北や南を行ったり来たりしながら、掘削するように広げていくと、徐々に
「エリアごとの酸のレベル」
がわかるようになり、
少しずつ
「酸の向こう側の味わいが拾えるようになってくる」
ことが実感できると思います。
個人的にはこうしてゆっくり広げていくのが良いと思います。
いきなり、飛び越していってみても良いですが、
「酸の壁」
に再び阻まれるかもしれません。
まあそれもまた一興。
また出たな~!と立ち向かってみても良いかもしれません。
要は「色々飲んでみる」
ということですから。
気付くと「酸の許容できる幅」が広がっている
そうして飲んでいくうちに、自分の
「酸の許容できる幅」
が広がっていくのに気づくと思います。
ある日突然、ふと
「ワインを長く飲んでいる人の言ってる言葉」
がわかる日が来ます。
そうすると、雑誌などの有名テイスターのコメントもより深く理解できるようになることでしょう。
よりワインの世界が面白く、感じられるはずです。
ちなみに酸のボリュームについては単純な緯度の南北だけではなく、
標高の高さや収穫の時期
などによっても左右されますので、余裕があったら意識してみてください。
おわりに
いかがでしたでしょか。
「酸の壁」問題。
主に初心者の方に向けた内容でしたが、
一つの方法論として楽しんで頂けたら幸いです。
「酸の壁、突破したよ!」という方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
では、また。
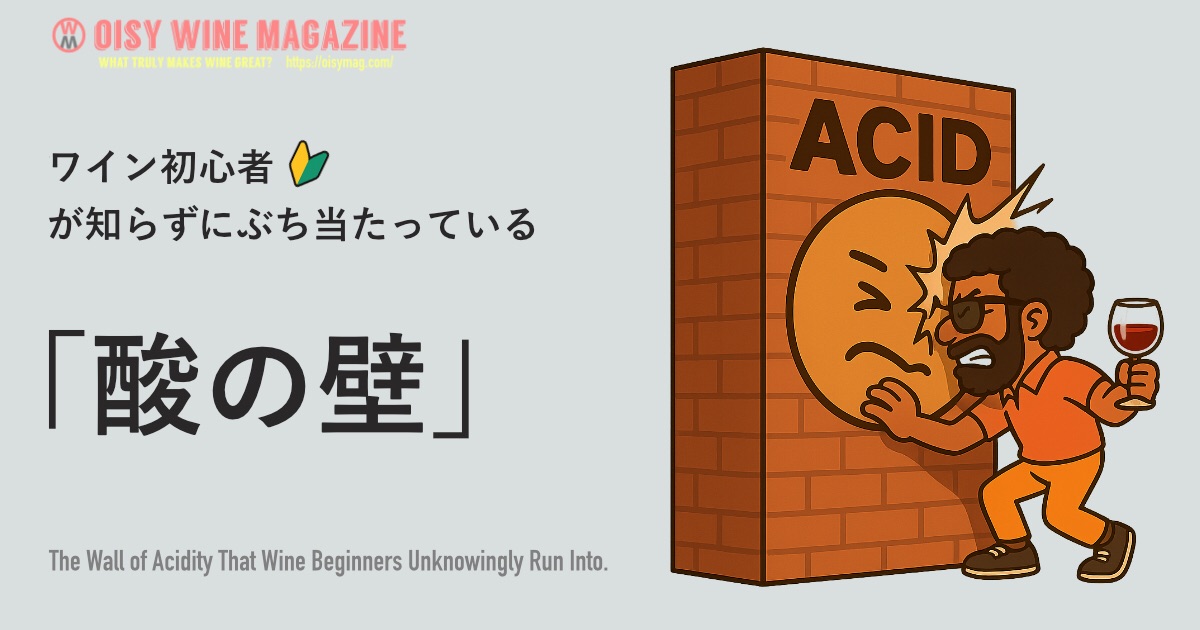



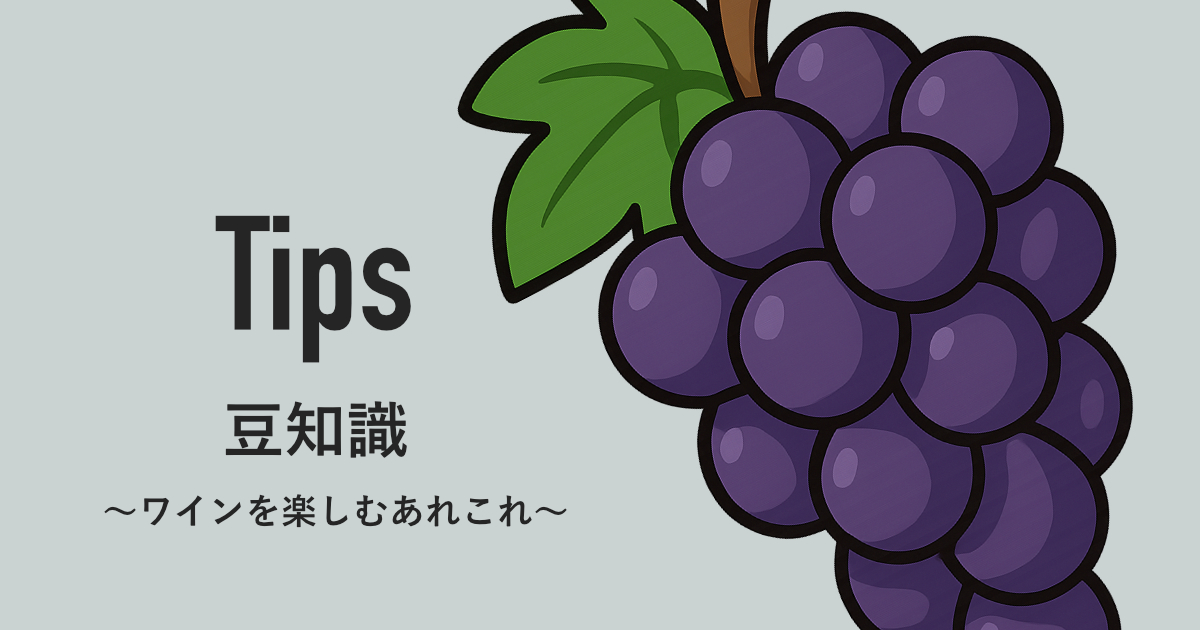
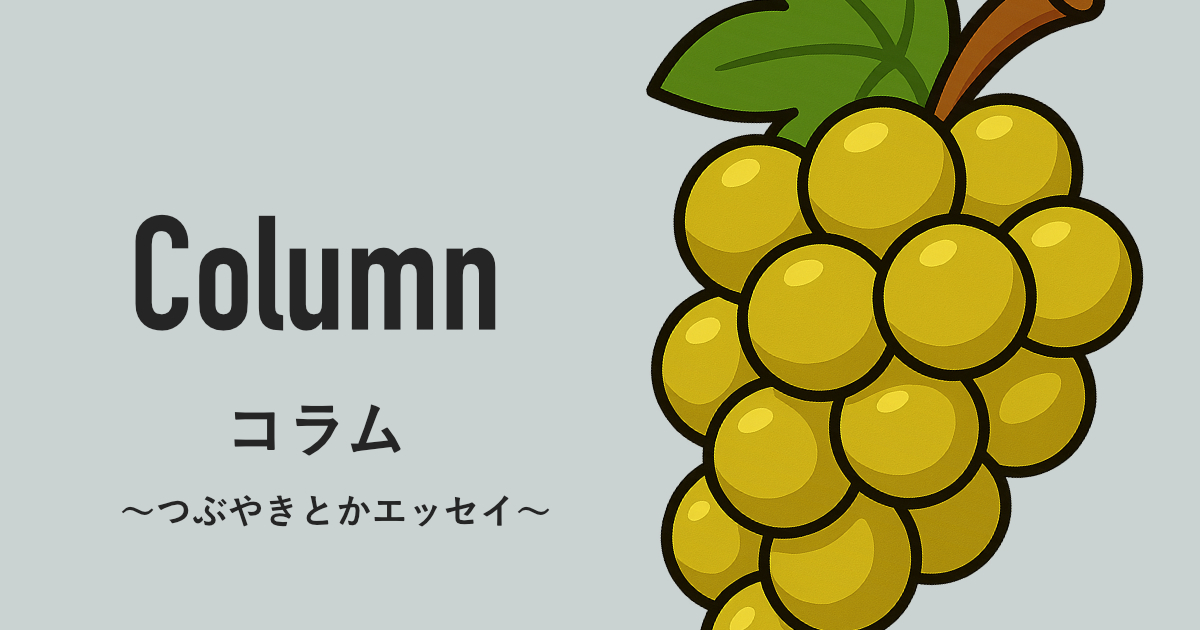


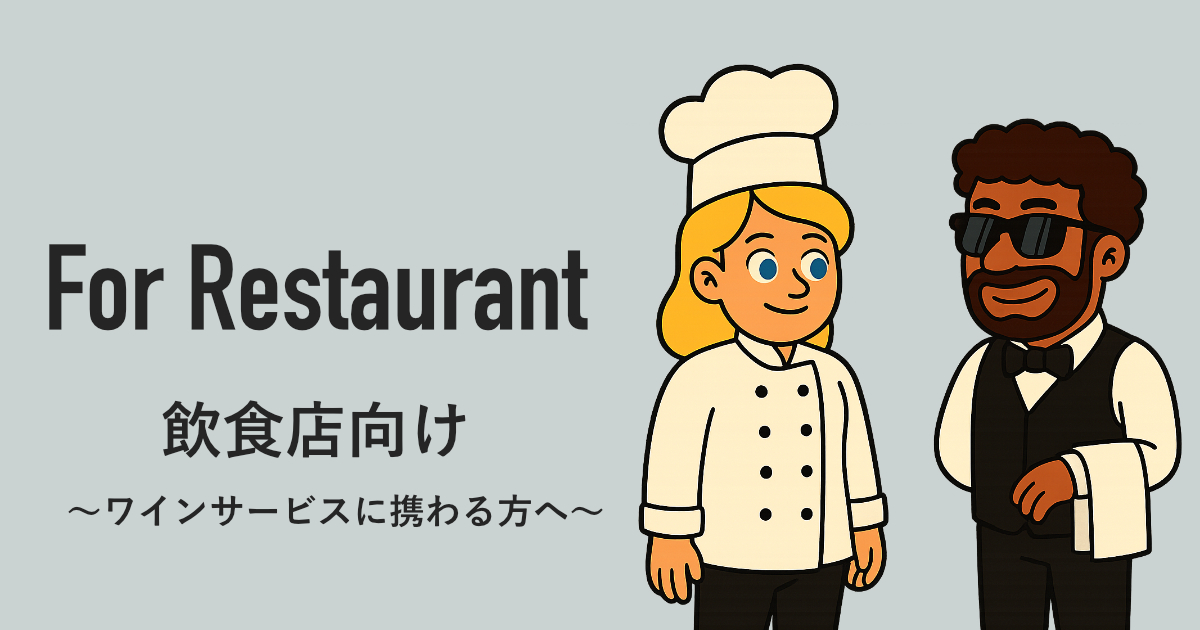


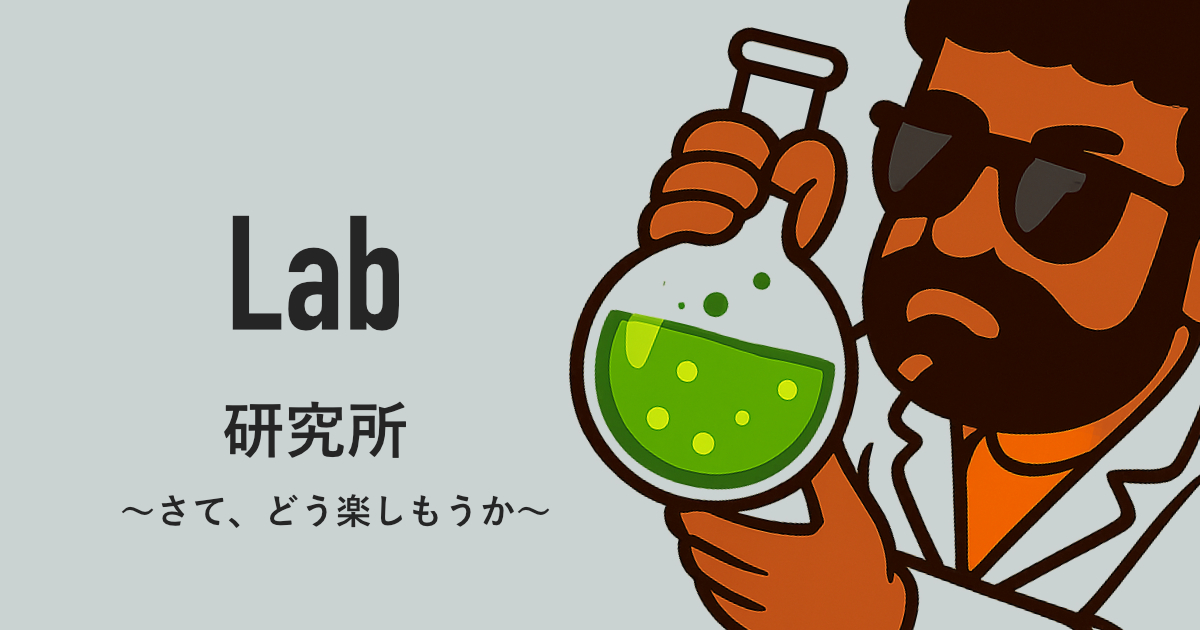





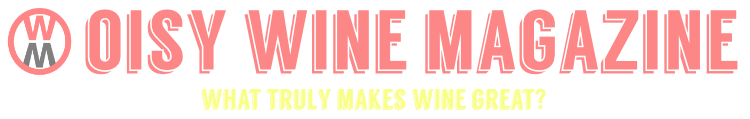
コメント